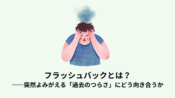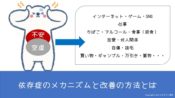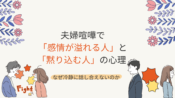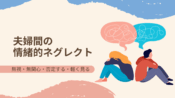【人を信じるのが怖い】対人不信の原因と改善方法
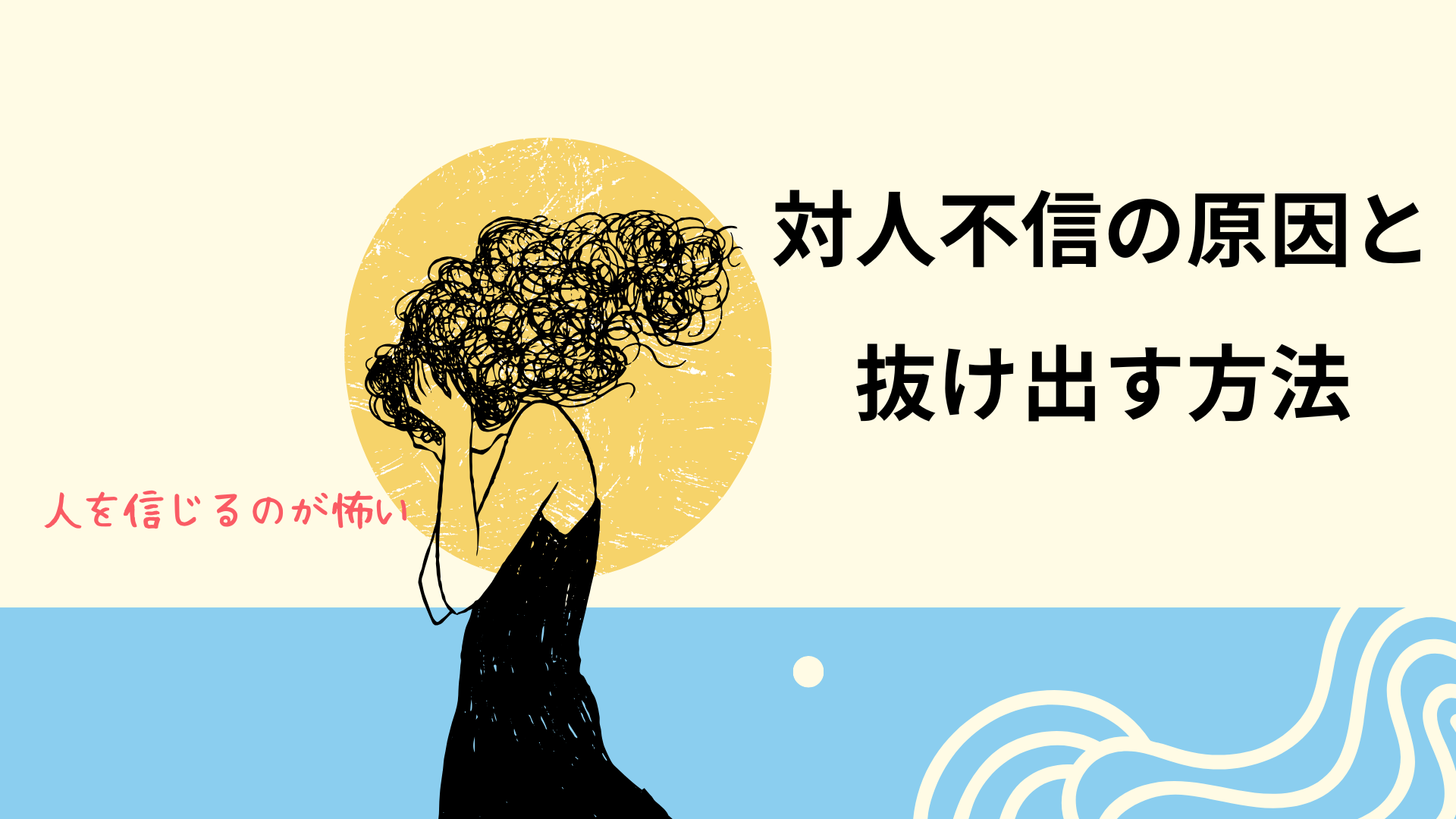
東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
「人を信じられない」
「いつも身構えてしまう」
「好意の裏を読んでしまう」
このように、「人と関わること」に不安を感じてしまう方は少なくありません。
この記事では、「対人不信」の背景にある4つの要因と、そこから少しずつ抜け出していくためのヒント、そしてカウンセリングができるサポートについてお伝えします。
対人不信の4つの要因
① 過去の裏切り経験
まず最初に挙げられるのは「信じていた人からの裏切り」や「傷つけられた経験」です。
たとえば、仲が良いと思っていた親友の陰口や裏切り、恋人の浮気、学校や職場での仲間はずれや、味方になってくれる人の不在・・・。
こうした経験は、人を信じる基本姿勢や社会への信頼感を大きく損ないます。
とくに、信頼していた相手からの裏切りは深く心に残りやすく、「また同じことが起きるかもしれない」と警戒心が抜けなくなります。
これは考えてみれば当然です。脳も身体もこころも、裏切りによる苦痛を記憶するため、次に同じようなことが起きないように注意を怠らないことで、自分を守ろうとするのは必要なことだからです。
けれども、この警戒心が対人不信感を生みます。なかなか、人がバランス良く生きるのは難しいことです。
ちなみに、このような裏切り体験から立ち直るのは容易ではありませんが、立ち直ることができた人というのは、強い人ではなく、他にも信じて頼れる人がいた人です。
② 自尊心の低さや自己不信
次に、「自分には人から愛される価値がないのでは」と感じてしまう自尊心の低さがあります。幼い頃に十分に認められなかったり、失敗や欠点ばかりを指摘され続けたりすると、自分自身への信頼感(=自己肯定感)が持ちにくくなります。
すると、「どうせ自分なんか」「信じても、どうせ裏切られる」といった気持ちが強くなり、人との関係にも投げやりになってしまいやすいのです。
例えば、相手が好意的な時にも「本心ではないのでは」と疑ってしまうこともあります。
これは単なる性格ではなく、生育歴や心の傷に根ざした“生きのびるための戦略”であることが多いのです。しかし、この自己不信は、信頼関係の形成を難しくし、ますます孤独を深めてしまうという悪循環を生みます。

③ 現代社会の構造的な不安と孤立
わたしたちが生きる現代社会は、本音で人とつながることが難しい時代でもあります。
SNSでは誰もが“見られる自分”を演じ、職場では成果や効率が重視され、家庭や恋愛においても「素の自分」を見せることがむずかしいのです。
すると、こころを開くことがリスクのように感じられ、「信じていいのか」「裏切られるのではないか」といった警戒心が常に働いてしまいます。
そのため、人といても孤独を感じたり、表面的なやりとりばかりが続いたりして、「本当の信頼関係なんて築けるのだろうか」と感じてしまうのです。

④ C-PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害)
C-PTSDは、子ども時代から長く続いた心の傷――たとえば、家庭内の不適切な養育、ネグレクト、いじめ、DVなど――によって、こころと身体に「人は信じられない」という感覚が根づいてしまうことです。
これは一時的なショックとは異なり、繰り返される傷つき体験のなかで、「助けを求めても無駄」「どうせ誰もわかってくれない」という無力感が身に染みついた体験です。
すると、大人になっても、対人関係を築くことに怖れを感じたり、人との距離感が極端になったりします。
過去と似た状況に出くわすと、強い不安や怒りに取り憑かれてしまう“感情のフラッシュバック”に苦しむ人も少なくありません。
C-PTSDは4つ全てに通底する
ここまで挙げてきた「過去の裏切り」「自己不信」「現代社会の孤独」といった要因は、実はすべてC-PTSDに深く関わっています。
C-PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害)とは、子ども時代から長期にわたって繰り返された心の傷――たとえば、虐待、ネグレクト、いじめ、家庭内の支配や無関心――によって、「誰も信じられない」「誰も助けてくれない」という感覚が、こころと身体にしみ込んで、警戒し攻撃的になったり、不安が強くて何事にも回避的になるなど、日常生活や対人関係にさまざまな困難をもたらしている状態を指します。
このような体験には、信頼していた大人に助けてもらえなかった経験(=子どもにとっての裏切り体験)(①)、ありのままの自分を受け入れてもらえなかった痛み(②)、安心してつながれる場をもたずに育った孤独(③)が、すべて含まれています。C-PTSDは、対人不信の要因に通底しているのです。
ですから、C-PTSDの人が「人を信じられない」と感じるのは、当たり前です。
それは、性格の問題やわがままではなく、サバイバルの結果です。
対人信頼感を回復するためには、まず、この理解に基づいて、自分を責めず、ここまで頑張ってきた自分に感謝とねぎらいを伝えて、自分のケアをする、少しずつ自尊心や自己肯定感を獲得することが必要です。

人を信頼できるようになるために
対人不信は、すぐに「克服する」ことは難しいかもしれません。
でも、少しずつ「信頼の回路」を育てていくことはできます。その4つのヒントをご紹介します。
① 物事への信頼
「お守りのチャームを見ると安心できる」「好きなお茶を淹れて飲むとホッとできる」「散歩に出るとリフレッシュできる」など、持ち物や行為を通じて、自分が「安心する」「ホッとする」「スッキリする」ことはありますか?
まずは、こういった物や行為への信頼を確認してみましょう。

② 動植物への信頼
四季折々の緑やお花を見て、「今年もきれいだな」と思う気持ち。
観葉植物にお水をあげると、元気に育ってくれる手応え。
好きな動物に触れることや、写真や動画を見て「かわいいなぁ」と思うことも、相手との信頼関係です。
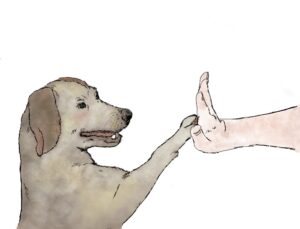
③ 人を部分的に信頼
いきなり誰かを100%信頼するのは誰にとっても難しいことです。まずは、部分的に信頼できるところを探してみましょう。
例えば、「この人は感情的な物言いはしないな」とか、「この人はいつも、時間に余裕を持って返事をくれるな」とか、「この人はいつも“大丈夫?”と声をかけてくれるな」のように。相手の「その点は信頼できるかも」と仮置きしてみるのです。
全面的に信頼することは不安や恐怖が伴うけれど、部分的に認めるなら、脅かされないで認知しやすくなります。
④自律神経を整える
こころと身体が警戒していると、自律神経も交感神経が優位になりっぱなしで、わずかな刺激にも強く反応しやすくなります。
自律神経を整えて、安心感、信頼感の土台を作りましょう。
■6秒吸って、8秒で吐く呼吸
ゆっくり長く吐くことで副交感神経にスイッチが入り、脳が「今は大丈夫」と認識しやすくなります。
■足裏グラウンディング
椅子に座り、かかとで床をトン、トンと軽く押す。足裏の感覚に意識を向けると、「いま・ここ」に戻る感覚が育ちます。
■温かさを感じるセルフハグ
胸や肩を両手で包み、10秒ほど静かに呼吸。皮膚刺激とぬくもりがオキシトシンを分泌し、安全を感じやすくなります。
日頃から自律神経を整えて、心身ケアすることが、自分を信じる力となり、対人関係においても相手を許容できる、穏やかに待つ力を持てるようになります。
カウンセリングにできること
対人不信が強い方、C-PTSDの方にとって、「人とつながる」「助けを求める」といった行為そのものが大きな勇気を要することです。
そのため、まずは前項でご紹介したような、「もの」「自然」「部分的な信頼」「自律神経を整える」といったステップを少しずつ試していくことが大切です。
そして、少しでも「誰かに話してみようかな」という気持ちが芽生えたときは、専門家に相談してみるタイミングです。
カウンセリングでは、以下のようなプロセスが可能になります:
■安心できる関係性の中で
自分のペースで話せること、無理に話さなくてもよいこと、守られた空間であること――これらが安心の土台になります。
■感情を丁寧に扱いながら
言葉にならない思いや、身体に残る違和感・緊張も、カウンセリングの場では大切な“メッセージ”として大切に取り上げて扱います。
■少しずつ信頼や自己肯定感を取り戻していく
「自分のままで大丈夫」と思える経験を重ねることで、自己肯定感を獲得し、自分への信頼感を取り戻していきます。
SE(ソマティック・エクスペリエンシング)によるアプローチ
SEは、身体の感覚を入り口にトラウマを癒す方法です。
C-PTSDの方は、頭では「大丈夫」と思っていても、身体が緊張や恐怖を記憶していて、ふとしたきっかけで過去の感覚がよみがえることがあります。
SEでは、「今この瞬間の体の安全感」に焦点を当て、過去の凍りついた反応や過覚醒を少しずつ解放していきます。
たとえば、「足の裏の感覚を感じる」「呼吸がどこまで入っているかに気づく」「安心したときの身体の変化を味わう」といった、小さな体感覚の変化を積み重ねることで、「もうあの時とは違うんだ」と、神経系レベルで安心を取り戻していきます。
パーツ理論(IFS:内的家族システム)によるアプローチ
C-PTSDの方の中には、「自分の中に、矛盾する気持ちが同時にある」と感じる方も少なくありません。
たとえば、
■「人とつながりたい」気持ちと「怖くて避けたい」気持ち
■「もう終わったはずなのに、過去が何度もよみがえる」苦しさ
■「感情を感じたい」けれど「感じたら壊れてしまいそう」な怖さ
IFSでは、こうした気持ちを、自分の中にいる様々な「パーツ(部分)」の声として扱います。
■傷ついた「インナーチャイルド」のようなパーツ
■その子を守ろうとして頑張ってきた「守り手」のパーツ
■感情を感じさせないようにフリーズさせる「遮断するパーツ」
こうした“内なる家族たち”と対話を重ねていくことで、それぞれのパーツの役割や願いを理解し、内的な安心感と一体感を取り戻していくことができます。
SEやIFSのアプローチでは、いきなり過去を語ることを求められるのではなく、「今の自分の感覚」「出てきているパーツの声」に寄り添うところから始まります。「過去の話をするのはつらい」という方にも向いています。
はこにわサロン東京では、対人不信・C-PTSDのカウンセリングを行っています
ご予約はこちら
対人不信・まとめ
「人を信じられない」と感じるのは、とてもつらく、孤独なことです。
けれども、そこには、裏切りや拒絶、孤立を生き延びてきた背景があることを理解する必要があります。
対人不信は、決して「弱さ」や「わがまま」ではなく、こころと身体があなたを守ってきた証です。そのことに気づき、ご自身を責める気持ちを一旦保留してみてください。
まずは、無理なくできることから。「ホッとするモノ」「安心できる自然」「部分的に信頼できる誰か」「呼吸や体の感覚」など、今ここで感じられる安全な手がかりをひとつひとつ育てていくことで、自分自身との信頼が育ち、人とのつながりも少しずつ楽になっていきます。
C-PTSDや対人不信の方にとって、カウンセリングは「人とつながる練習の場」として役立つことがあります。無理に話さなくてもいい。今のままでいい。そんな関係の中で、安心や信頼を取り戻していくことは可能です。
もし、少しでも「人を信頼して繋がりたい」お気持ちが出たら、その気持ちを大切にしてみてください。
信頼感を取り戻していきましょう。