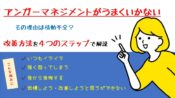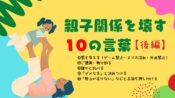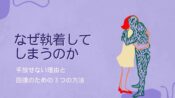産後うつ:症状と治療・予防策・セルフケア・家族にできること
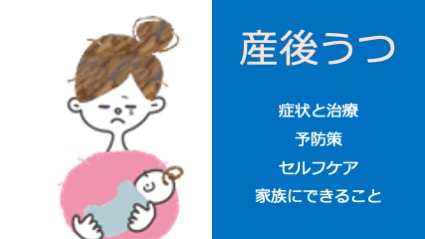
東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
産後うつとは、出産後に発症する抑うつ状態であり、ホルモンの急激な変化、育児のストレス、睡眠不足、社会的孤立などが関与していると考えられています。
出産後の母親の約10〜15%に発症するとされ、放置すると長引きやすく、育児や日常生活に大きな影響を及ぼします。
産後の女性は身体的・精神的に大きな変化を経験するため、一時的な気分の落ち込みは珍しくありません。しかし、産後うつは一時的なものではなく、長期間続き、日常生活に支障をきたす状態です。
産後うつの主な症状
1)気分の落ち込み、涙もろくなる
2)強い不安や焦燥感(子どもをうまく育てられるか不安になる)
3)極度の疲労感、無気力(何もしたくない、育児が苦しい)
4)食欲の低下または過食
5)不眠または過眠(寝つきが悪い、夜中に目が覚める)
6)集中力の低下、物忘れがひどくなる
7)赤ちゃんへの関心が薄れる、または過剰に心配しすぎる
8)罪悪感や無価値感を感じる(「母親失格だ」「こんな自分ではダメだ」)
9)イライラしやすくなる(夫や家族、赤ちゃんに対して怒りを感じる)
10)育児や生活への興味を失う
11)「消えたい」「死にたい」などの希死念慮

産後うつの診断基準〜DSM-5(精神疾患の診断基準)
産後うつは、「大うつ病」の一種として分類され、以下の基準を満たす場合に診断されます。
(以下の症状のうち5つ以上が、2週間以上続く)
■抑うつ気分(ほぼ毎日、1日中続く)
■興味や喜びの喪失(以前は楽しかったことが楽しくない)
■食欲の変化(食べられない、または過食)
■睡眠障害(不眠または過眠)
■精神運動の遅延または焦燥感(動作が遅くなる、またはソワソワする)
■疲労感や気力の低下(常に疲れている、何もする気がしない)
■無価値感や過剰な罪悪感(「母親失格だ」と思う)
■集中力の低下、決断力の低下(本を読めない、家事が手につかない)
■死についての考え(「いなくなりたい」「死んだほうが楽」などの希死念慮)
産後うつの治療
① 心理療法(カウンセリング)
■カウンセリングを通じて、母親の悩み、ストレス、不安を軽減する。
■必要なサポート得られるよう検討する。
② 薬物療法(医師の処方が必要)
■薬物で不安の軽減、抑うつの軽減を行う。
■医師と相談し、授乳との兼ね合いを考えながら使用する
③ 休養とサポートの確保
■家族・パートナーの協力を得る(育児を一人で抱え込まない)。
■育児支援サービス(ファミリーサポート、ベビーシッターなど)の活用
■十分な睡眠を確保する
産後うつを防ぐには?(予防策)
産前から「助けを求める準備」をしておく
■妊娠中から夫・家族と家事・育児の分担を話し合う
■外部サポート支援について調べておく
睡眠不足を最小限にする
■赤ちゃんが寝ている間は、一緒に休む(家事を優先しない)
■夫や家族に夜間授乳を交代してもらう(ミルクや搾乳を活用)
孤立しないようにする
■育児サークル、ママ友、オンラインコミュニティなどで交流する
■専門家(助産師、保健師、カウンセラー)に相談できる環境を作る
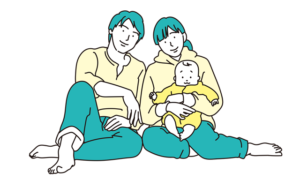
産後うつのセルフケア
自分を責めない
出産は母親にとってとても負担の大きいイベントです。
心身のコンディションを崩す方は決して少なくありませんし、だからこそ母親の負担を減らす子育てに環境調整していくことが大切なのです。
「自分のせい」と感じてしまったら、「これも産後うつの症状だな」と気づいてくださいね。
ひとりにならない
ひとりになると自分を責めてしまいやすくなります。
できるだけ、周囲から助けてもらうようにしていきましょう。
具体的には、夫・家族や友だちに話を聞いてもらったり家事育児をサポートしてもらいましょう。
できることだけやればいい
親子が今日をちゃんと生きていたら(もしできたら笑顔で)それだけで満点です。
それ以外のことは、いずれやる(保留)でOKです。
温かい食事を摂る
自分の食事を準備するのは難しいことも多いかもしれませんが、できるだけ食事が取れるように工夫すること。
また、温かい食事を摂れると、セルフケアになります。
少しでも自分の時間を作る
家族等の助けを借りて、少しでも自分の時間を持ちましょう。
自分の時間、というのは、家事をする時間ではなくて、自分が心地よく過ごす時間のことです。
お風呂に入る、好きな飲み物を飲む、うとうとする。
好きな香りや音楽など、ホッとできることを取り入れてください。

産後うつ・家族にできること(夫・家族のサポート)
産後うつを理解する
■「産後うつは甘えではなく、病気」と理解する。病気を甘えということは暴力(ハラスメント)です。
■「気合で乗り越えろ」などの言葉は絶対NG(DV/モラハラです)
具体的な行動で支える
■「何か手伝う?」ではなく、「〇〇するね」と具体的に動きましょう。
■育児・家事を積極的に分担する(夜間の授乳、オムツ替えなど)
「感謝・ねぎらいの言葉」を伝える
■「いつも頑張ってくれてありがとう」と感謝を言葉にして伝えましょう
■「君は十分やってるよ」と肯定する言葉かけをします。
外部のサポートを活用する
■家族だけで抱え込まず、専門家に相談する(保健センター、助産師、カウンセラー)
■育児支援サービス(ベビーシッター、ファミリーサポート)を活用する

産後うつ・まとめ
■出産は女性にとって、とても負担の大きいライフイベントです。「誰もがすること」「当たり前のこと」などと甘く見てはいけません。
■産後うつは、「母親だから」「赤ちゃんがかわいいから」では防げるものではありません。
■「助けを求めていい」「休んでいい」「一人じゃない」と考えられることが回復の一歩です。
■家族や周囲も、「母親だけが頑張るもの」ではなく、「みんなで育てるもの」という意識を持つことで、産後うつを防ぐ・回復することができます。