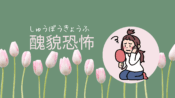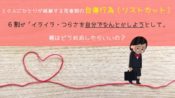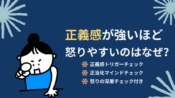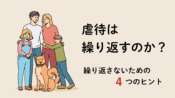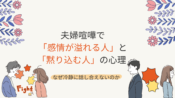パニック障害とは?症状・なりやすい人の特徴・治療・ケアの方法

東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
パニック障害とは、突然の強い不安や恐怖に襲われ、動悸・息苦しさ・めまいなどの発作(パニック発作)を繰り返す病気です。パニック発作は命に関わるものではありませんが、本人にとっては「このまま死ぬのではないか」と思うほど強烈な恐怖を伴います。
発作が起こることへの不安(予期不安)や、人前で発作が起こることを恐れて外出を避ける(広場恐怖)など、生活に大きな影響を与えることもあります。
パニック発作の主な症状(突然、激しい不安や恐怖を感じる)
■動悸・心拍数の増加
■息苦しさ、過呼吸
■めまい、ふらつき
■発汗、震え
■胸の痛みや圧迫感
■吐き気や腹部の不快感
■手足のしびれ、冷感・熱感
■現実感の喪失(自分が自分でない感覚)
■「このまま死んでしまうのでは」「発狂するのでは」という強烈な恐怖
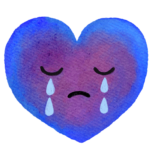
パニック発作が続くことで生じる影響
予期不安
予期不安とは、「またパニック発作が起こるのではないか」と強く恐れる状態のことです。
実際に発作が起きていなくても、「いつどこで発作が起こるかわからない」という不安が常に頭にあり、日常生活に支障をきたします。例えば、以前発作を経験した場所や状況を思い出すだけで、不安が高まり、動悸や息苦しさを感じることもあります。
この不安が続くと、「発作を避けるために行動を制限する」「人と会うのを控える」といった回避行動につながりやすくなります。
広場恐怖
広場恐怖とは、「助けが得られない場所で発作が起こったらどうしよう」という恐怖から、特定の場所や状況を避ける状態を指します。
例えば、「電車やバス」「映画館」「エレベーター」「人混み」など、自分がすぐに逃げられないと感じる場所を避けるようになります。
広場恐怖が強くなると、外出自体が困難になり、日常生活に大きな影響を及ぼします。回避が続くと行動範囲が狭まり、閉じこもりがちになるため、抑うつ状態につながることもあります。

パニック障害になりやすい人の特徴
ストレスに敏感な人
ストレスに敏感な人は、日常のプレッシャーや環境の変化に強い不安を感じやすく、交感神経が過剰に働く傾向があります。
特に、対人関係のトラブルや仕事のプレッシャーなど、ストレスが蓄積すると、身体の過剰な反応(動悸・息苦しさなど)が起こりやすく、これがパニック発作につながることがあります。
もともと不安を感じやすい性格の人は、発作後に「また起こるのでは」と恐れる予期不安を抱きやすく、さらに発作を繰り返す悪循環に陥りやすいです。
完璧主義・責任感が強い人
完璧主義で責任感が強い人は、「失敗してはいけない」「常にしっかりしなければ」と自分に過度なプレッシャーをかけやすいため、緊張状態が続きやすくなります。
そして、自分の感情や疲労を後回しにすると、気づかないうちにストレスを溜め込み、ある日突然パニック発作を起こすことがあります。
また、「弱音を吐いてはいけない」「人に迷惑をかけてはいけない」と思い込んでいると、発作が起きたときに強い自己否定を抱え、さらに不安が悪化しやすいです。
トラウマを抱えている人
幼少期の虐待、いじめ、事故、災害、DVなど、過去に強い恐怖を経験した人は、心身が「危険な状況に備えなければならない」という防衛反応を過剰に発動しやすくなるため、パニック障害のリスクが高まります。
特に、トラウマ体験が未処理のまま残っていると、ストレスがかかったときに突然フラッシュバックのような形で発作が起こることがあります。
脳が「安全な状態でも危険だ」と誤認しやすくなるため、過度な警戒心や予期不安を持ちやすく、日常生活の中で繰り返し発作が起こることがあります。
遺伝的要因
パニック障害は、遺伝的な要素が関与していることが指摘されており、家族に不安障害やパニック障害の人がいる場合、発症リスクが高まるとされます。これは、脳内の神経伝達物質(セロトニン・ノルアドレナリンなど)のバランスが遺伝的に影響を受ける可能性があるためです。
ただし、「親がパニック障害だから自分も必ずなる」というわけではなく、ストレスの多い環境や性格傾向が重なることで発症しやすくなると考えられます。
生活習慣の乱れ
不規則な生活や睡眠不足、カフェインやアルコールの過剰摂取などは、自律神経のバランスを乱し、パニック障害の発作を引き起こしやすくする要因となります。特に、睡眠不足や慢性的な疲労は、不安を感じる脳の働きを過敏にし、ストレスに対する耐性を下げます。
また、カフェインやアルコールは一時的に気分を高める作用があるものの、血圧変動や心拍数の増加を引き起こし、発作の誘因になることがあります。
健康的な生活習慣はパニック障害を防ぐためにとても大切です。
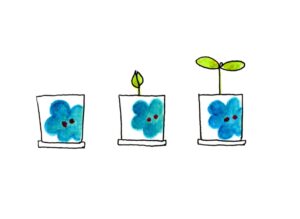
パニック障害の診断基準(DSM-5より)
以下のうち4つ以上が突然発生し、数分以内にピークに達する発作が繰り返される
■動悸、心拍の増加
■発汗
■震え
■息切れ、息苦しさ
■窒息感
■胸の痛みや不快感
■吐き気や腹部の不調
■めまい、ふらつき、気が遠くなる感覚
■寒気または熱感
■しびれやうずき(感覚異常)
■現実感の喪失、自分が自分でない感覚(離人感)
■「気が狂うのでは」「死ぬのでは」という強い恐怖
さらに、以下のいずれかが1ヶ月以上続く
■予期不安・・・また発作が起こるのではないか」という不安
■行動の変化・・・発作を避けるための過度な回避行動
パニック障害の治療法
薬物療法
医師の診断・処方のもと、不安症状を緩和する薬物が使われます。
カウンセリング
カウンセリングを通じて、発作のメカニズムを学び、不安を緩和する方法を学びます。生活の見直し、ストレスケア、セルフケアを学びます。過去のトラウマが影響している場合は、その原因を探り、理解・整理することで、不安や発作を和らげていきます。生活全般の不安や生きづらさについても、改善を目指します。
生活習慣の改善
発作を防ぐための生活習慣の改善はとても大切です。睡眠が十分取れているか、運動習慣を作る、食事の見直し、また、カフェインやアルコールを控えることで神経の興奮を防止します。不安を感じないで行える趣味・活動、リラックスできる活動についても検討が望ましい。

パニック発作が起こったときの対処法
①ゆっくり呼吸する
4秒かけて鼻から息を吸い、8秒かけて口から吐く(腹式呼吸)。過呼吸を防ぎ、落ち着きやすくなる。
②「発作は危険ではない」と自分に伝える
「これはパニック発作。必ずおさまる」と繰り返し心の中で言う。
③地面や物に触れる
足裏の感覚や、冷たい飲み物、持ち物の質感に意識を向けると、不安が和らぐ。
④安全な場所で座る
できるだけ静かな場所で深呼吸し、回復を待つ。
⑤誰かに伝える
信頼できる人がそばにいれば、「少し息苦しい」と伝えるだけでも安心感が得られる。
パニック発作を予防する生活習慣
規則正しい睡眠をとる
睡眠不足は自律神経を乱し、不安を増幅させます。
最低6時間以上で、起きた時に「よく眠れた」と感じられる睡眠をとりましょう。
適度な運動をする
ウォーキングやストレッチなど軽い運動は、ストレスを和らげ、心を安定させてくれます。
カフェインやアルコールを控える
カフェインは神経を過敏にします。
アルコールは一時的に気分を和らげてくれますが、アルコールがさめると不安が増します。
リラックス・リフレッシュする時間を持つ
好きなこと、没頭できることをする時間を持ちましょう。
ゆっくり落ち着けるもの、歌を歌う・笑うなどの発散系、どちらも大切です。
バランスの良い食事をとる
甘いもの・糖質のとりすぎを避け(血糖値の急上昇を防ぐため)、バランスの取れた食事を心がけましょう。

周囲の人にできること
パニック発作が起きたときの対応
■「大丈夫、ここにいるよ」と落ち着いた声で安心感を与える
■「気にしすぎだよ」と言わず、本人の不安を否定しない
■深呼吸を促し、一緒にゆっくり呼吸する
日常でできるサポート
■無理に外出や挑戦を強要しないこと。強要はプレッシャーを与え、不安にさせてしまいます。
■「一緒にできること」を提案する(短時間の外出など)
■焦らず、回復のペースを尊重する
パニック障害・まとめ
パニック障害は、突然の激しい不安や発作を繰り返す疾患で、予期不安や回避行動によって生活に影響を及ぼします。適切な治療とセルフケアを行って、回復することが可能です。
周囲の人は「気にしすぎ」ではなく、「つらさを理解し、寄り添うこと」が大切です。安心できる環境を作ることが、回復の大きな支えになります。