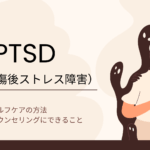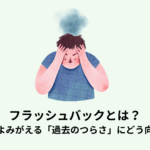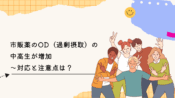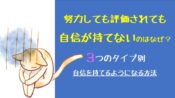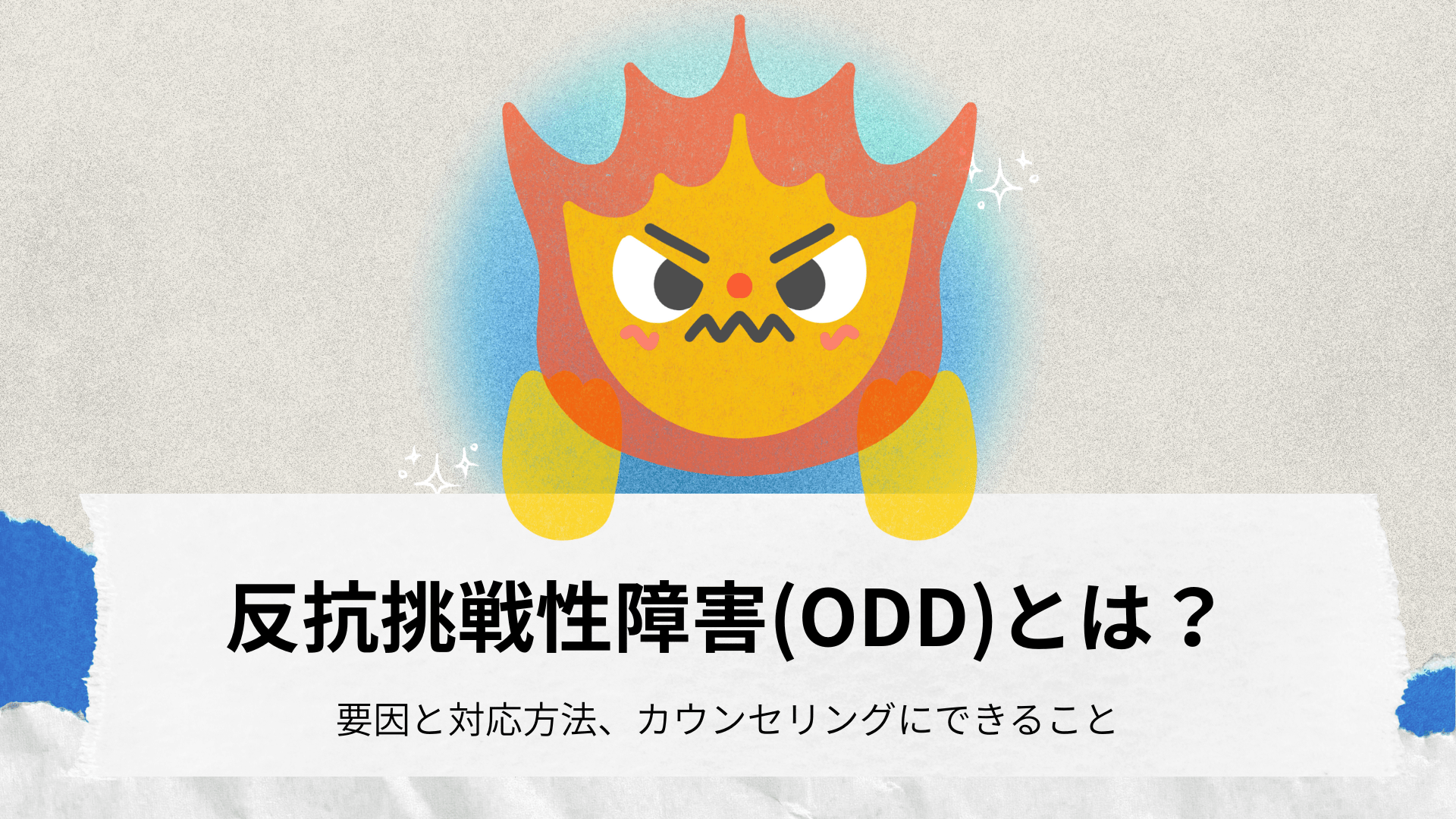C-PTSDとは?原因・症状・回復へのセルフケアとカウンセリング
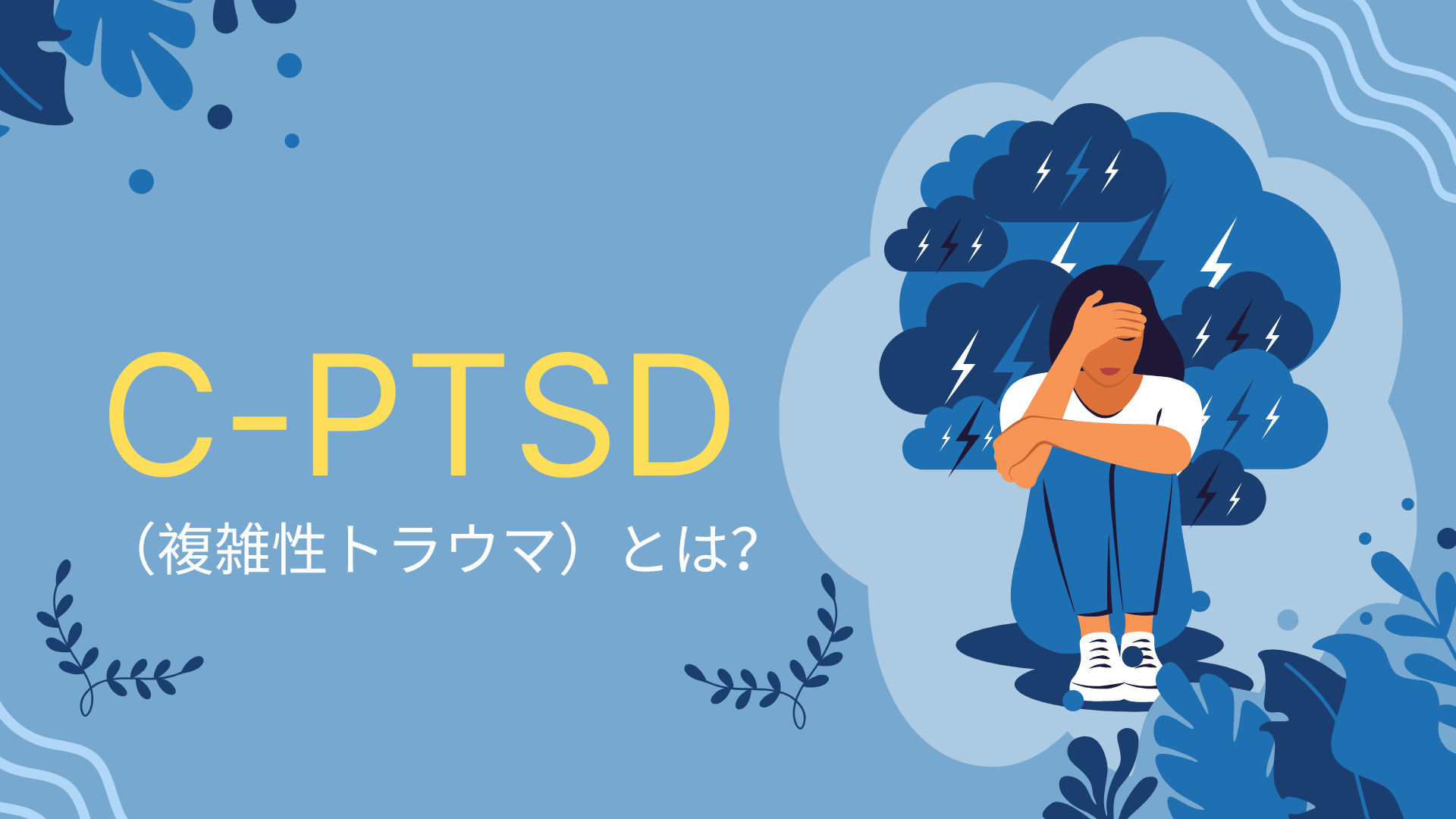
東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
今回は、近年注目されている「C-PTSD(複雑性PTSD)」について、原因や症状、治療、日常でできるケアについてわかりやすく説明します。
まずは、混乱されやすい、「トラウマ」と「PTSD」について簡単に説明するところからお話したいと思います。
トラウマとは?
トラウマとは、心が圧倒され、処理しきれないほどの強いストレス体験によって生じる「心の傷」です。
● 事故や災害
● 虐待や暴力
● いじめ
● 親からの無視や否定的な関わり
トラウマは単なる「嫌な思い出」ではありません。
神経や脳の働きに深く関わり、心身の反応として「フラッシュバック」「過覚醒」「無感覚」などを引き起こします。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは?
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、単発的で命に関わるような強い恐怖体験(例:災害・事故・暴力)によって発症します。
主な症状は以下の通りです。
● フラッシュバック(当時の恐怖がよみがえる)
● 過覚醒(いつも緊張している)
● 回避(似た体験を避けようとする)
● 感情の麻痺
PTSDは、急性の強いトラウマ反応に対して診断されます。
C-PTSD(複雑性PTSD)とは?
C-PTSD(複雑性PTSD)は、長期間にわたる反復的なトラウマ体験によって起こります。例えば:
● 家庭内での慢性的な否定や無視
● 長期間のいじめ
● 支配的・モラハラ的な関係
C-PTSDでは、PTSDの症状に加えて、次のような特徴が現れます:
● 強い見捨てられ不安
● 人間関係の困難
● 空虚感や感情の鈍麻
● 過剰な罪悪感や恥
これらは「性格」ではなく、長期的なトラウマが神経系や心の働きに影響した結果です。
C-PTSDの診断基準(ICD-11)
世界保健機関(WHO)のICD-11では、C-PTSD(複雑性PTSD)は以下の3つの要素で定義されています。
① PTSDの症状
C-PTSDには、まずPTSDと同じ以下の症状が見られます:
● 再体験:フラッシュバックや悪夢として当時の記憶がよみがえる。例えば、虐待を受けていた時の声や音が頭の中でよみがえり、今そこにいるかのように感じる。
● 回避:トラウマを思い出すきっかけを避けようとする。例えば、特定の場所や話題、人物を避ける、感情を麻痺させる。
● 過覚醒:常に神経が張りつめている状態。例えば、小さな物音にも驚きやすい、いつも緊張していて、夜もよく眠れない。
② 自己組織化の困難
C-PTSDでは、PTSDの症状に加えて「自己を安定して保つ力」にも困難が生じます:
● 自己否定:自分を「ダメだ」「価値がない」と感じる。例えば、何をしても自信が持てず、人の期待に応えられないと強く自分を責める。
● 感情調整の困難:感情が極端に揺れ動く。例えば、ささいなことで怒りが爆発する、突然虚しさや絶望感に襲われる。
● 人間関係の困難:信頼関係を築くのが難しい。例えば、相手に依存しすぎたり、逆に誰とも深く関わらないようにしてしまう
③ 長期間のトラウマ体験
C-PTSDの背景には、繰り返し長期間続くトラウマ体験があります:
● 幼少期の虐待やネグレクト
● 長期的な家庭内暴力(DV)
● いじめなどの継続的な対人ストレス
これらの体験は、「一度の強いショック」で生じるPTSDとは異なり、日常生活の中で慢性的に「安心できない状態」にさらされることによって、心や神経の発達そのものに影響を与えます。
他の疾患との関係
C-PTSDは、しばしば他の症状や診断と重なります。
● うつ病:無力感・自己否定
● 不安障害:過剰な警戒心
● 適応障害:ストレスへの耐性低下
● 愛着障害:対人関係の不安定さ
● アダルトチルドレン(AC):親子関係の影響
● 発達性トラウマ:幼少期からの慢性的ストレスが発達障害のように見える
● 解離性障害:圧倒される体験を切り離してしまう
これらは独立した診断名として扱われることもありますが、C-PTSDの影響による場合も少なくありません。
その場合は、C-PTSDを念頭に置いたケアや治療が必要です。
なぜC-PTSDは生じるのか
C-PTSDは、「逃げ場のない環境」で「繰り返しストレスを受ける」ことによって生じます。特に幼少期は、親や養育者との関係の中で「安心感」が育たないと、自律神経や脳のストレス反応が過敏になりやすいことが知られています。
● 安全基地の欠如:安心して甘えられる経験が少ない
● 慢性的ストレス:日常的な緊張や恐怖
● 支援の欠如:周囲に助けを求められない状況
このような条件が重なることで、脳が「常に危険な状態」と誤認し続けてしまいます。
なぜC-PTSDは治りにくいのか
C-PTSDは、単なる「トラウマの延長」ではなく、心や神経の土台に深く影響を及ぼす状態です。そのため、回復には長い時間がかかることが多いです。
長期間のストレスで神経が「安心」を忘れている
PTSDは単発の出来事で生じるのに対し、C-PTSDは虐待・ネグレクト・DV・いじめなど、長期的なストレス下で生じます。
このような環境では、子どもの頃から自律神経が「危険に備えるモード(交感神経や背側迷走神経)」に偏り続け、安心を感じるための神経(腹側迷走神経)が育ちにくいのです。
そのため、ストレスがない状況でもリラックスできず、常に心と身体が緊張している状態になりやすいのです。
「耐性の窓」が狭い
耐性の窓とは、心と身体が落ち着いていられる範囲のことです。
C-PTSDの方はこの範囲が非常に狭く、少しのストレスでパニック(過覚醒)や無気力(シャットダウン)に陥りやすい傾向があります。
例えば…
● 周囲の人の顔色にすぐに反応して疲れてしまう
● 人の評価に敏感でいつも自分を過剰に責め続けてしまう
● ちょっとした失敗で「もうだめだ」と全てを投げ出したくなる
「自己否定」のクセが深く根付く
長期間のトラウマ体験は、自己肯定感に深刻な影響を与えます。
「自分が悪いから虐待された」「誰も助けてくれなかったのは自分の価値がないから」といった考えが、無意識に刷り込まれやすくなります。
このため、回復の過程で支援や助けを受けることにすら抵抗を感じることがあります。
人間関係での「安心経験」が不足している
C-PTSDでは、人間関係そのものがストレス源であったことが多いため、「人と関わると安心できる」経験が乏しいのが特徴です。
結果として、信頼関係を築くことや、サポートを求めることが苦手になり、回復が遅れる要因になります。
だからこそ、C-PTSDの回復には「安心の体験を少しずつ積み重ねること」が重要です。
安全な関係の中で、落ち着き(腹側迷走神経)を取り戻しながら、感情調整力や自己肯定感を育てていくことで、少しずつ回復の土台が整っていきます。
C-PTSDの治療
C-PTSDの治療は、時間をかけて「安心の神経」を育て直すことから始まります。
C-PTSDの心理療法
● トラウマ焦点療法(EMDR、持続エクスポージャーなど)
● 身体志向のアプローチ(ソマティック・エクスペリエンシング、ポリヴェーガル理論に基づく介入)
● パーツ心理学(IFS):内なる「傷ついた部分」を安全に理解し癒やす
● 安定化とセルフケア:安心する感覚を日常で育てる
C-PTSDの薬物療法
必要に応じて、抗うつ薬や抗不安薬が補助的に用いられることがあります。
C-PTSDのセルフケア
C-PTSDの方は、カウンセリングや医療機関につながることが望ましいとご自分でわかっていても、つながりにくい特徴があります。これまでの体験から、人を信頼してサポートを得ることがなかなか難しいからです。ですので、まずは、自分でできるセルフケアから始めてみるのがおすすめです。
感情の記録
日記やメモに、その日の気持ちや出来事を書き出します。
● 例えば「今日は朝から不安だった」「人に会ったあと疲れた」
● 言葉にならないときは、色や絵で表現してもOK。
感情を表現することで、気持ちが少し楽になったり、「自分を大切にしてよい」と感じられるようになります。
身体ケア
C-PTSDのケアにおいて、身体のケアはとても重要です。というのは、トラウマは身体に深く刻まれているので、まずは、身体のケアを優先することは理にかなっているからです。
● 睡眠:可能なら寝る前にスマホを置いて、深呼吸をしてから眠る。
● 食事:一汁一菜でいいので、規則正しく食べる。
● 休養:疲れたら「少し横になる」「静かな音楽を聴く」など、短時間でも体を休める。
● 身体のこわばりがひどい時は、ストレッチや呼吸法を試してみる。
● マッサージや鍼、ロルフィングなどのボディケアが心地よく感じられる時は、取り入れてみるとよいでしょう。ただし、身体を触られることがストレスな場合は、やめておきましょう。
セルフコンパッション(自分に優しい言葉をかける)
C-PTSDの方は、自分を責める傾向が強くなりがちです。それも、トラウマの影響で生じています。ですので、お友だちにかけるような親切な言葉を自分にもかける試みをしてみてください。
● 「自分はダメだ」→「いるだけでOKだよ」
● 「失敗した」→「お疲れさま」
神経を落ち着ける習慣
C-PTSDの方は自律神経が大きく乱れていることが多いです。ですので、C-PTSDケアのために、自律神経を整えることは理にかなっており、また、とても効果的です。
● 深呼吸:ゆっくり吸って、長めに吐く
● セルフタッチ:胸や肩に手を当てて、手のひらの温かさを感じる。
● 軽い運動:散歩、ストレッチ、ラジオ体操など無理のない動きから始めてみる。
信頼を取り戻す
人に対する100%の信頼を回復する、というのは誰にとっても難しいものです。部分的な信頼から始めてみましょう。
● 生き物(ペット)への信頼を感じる
● 「この人のこの点は信頼できる」のように、部分的な信頼を見つけてみる
● 無理して話さなくてもよい人間関係を見つける
C-PTSD:カウンセリングにできること
はこにわサロンでは、C-PTSDでお悩みの方に、次のようなカウンセリングを行っています。
トラウマや神経の仕組みをわかりやすく説明
はこにわサロンでは、トラウマやC-PTSDの神経的・心理学的メカニズムを解説します。自分の苦しみが、自分のせいではなく、神経の反応であり、自分が自分を守ろうとしてきた結果であると知ることは、自尊心と自己肯定感を取り戻すために不可欠だからです。不安の強さやフラッシュバックなどに関しても、理由がわかると、ずっと向き合いやすくなります。
ソマティック・エクスペリエンシングとポリヴェーガル理論に基づいたカウンセリング
トラウマ体験は身体に記憶されるため、C-PTSDの方は、神経が過敏になりやすく、安心することやリラックスがとても難しいです。その理由をご説明し、心身を安心させるためにできること、例えばグラウンディングや呼吸法などの方法をご紹介します。環境調整を含め、あなたにとって取り入れやすい方法を検討し、実践していただきます。
いつも緊張していたり、すぐに怒りが爆発したり、無感覚になってしまいがちだったものが、少しずつ自分でコントロールできるようになっていきます。すると、少しずつ自分に自信が持てるようになっていきます。
安心できる枠組みの中での対話
トラウマ体験を話すことは、トラウマの再演・フラッシュバックを引き起こすリスクがありますので、無理に過去の出来事を話す必要はありません。ただ、溢れ出てくる思いや、今に紐づく過去の出来事をお話ししてもらうことで、整理して大切にしまい直すことができます。
箱庭・絵画療法や夢分析で「言葉にならない気持ち」を表現
自分の気持ちを言葉にするのが難しい時は、イメージの力を借りることができます。箱庭療法、絵画療法、夢分析などの方法を通じて、少しずつケアと自己理解をしていきましょう。
カウンセリングの方法は、ご一緒に相談しながら決めることができます。
こにわサロンでは、あなたが少しずつ「安心して生きられる」力を取り戻せるよう、専門的なサポートをご提供します。一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事