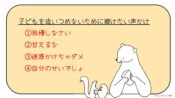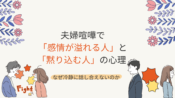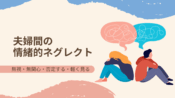反抗挑戦性障害(ODD)とは?要因と対応方法、カウンセリングにできること
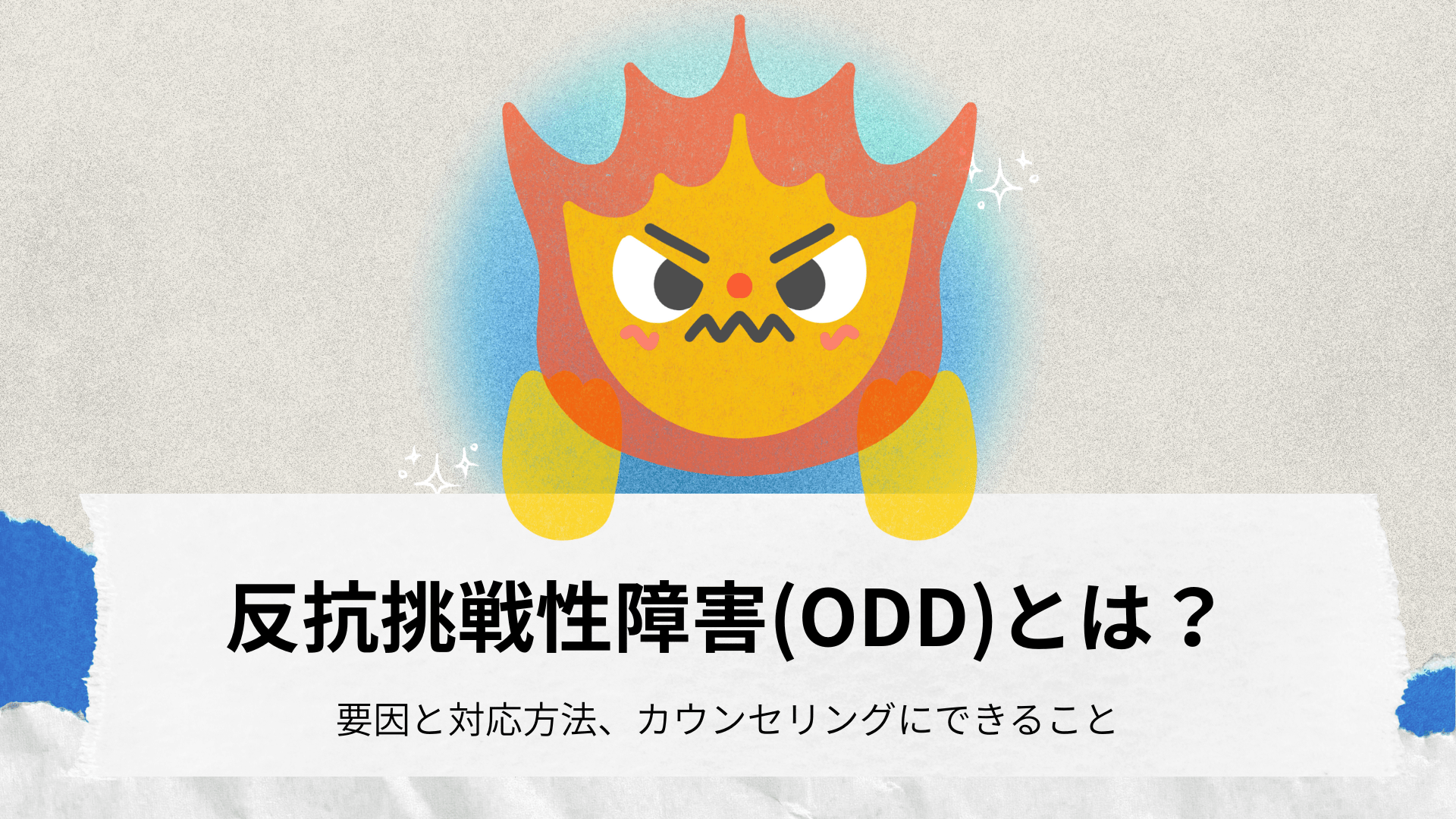
東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
反抗挑戦性障害(ODD)とは、年齢に不相応な強い反抗的・挑戦的態度や敵意が、6か月以上続く行動のパターンを特徴とする発達期の行動障害です。
家庭や学校での指示に反発したり、大人や権威に対して挑戦的な態度を取る、かんしゃくを繰り返すなどの行動が見られます。放置すると学業不振や対人関係の悪化につながり、将来的に素行障害や不安・抑うつを合併するリスクが高まります。この記事では、反抗挑戦性障害とは何か、要因と対応の方法についてできるだけわかりやすくお話していきます。
反抗挑戦性障害(ODD)の診断基準(DSM-5)
反抗挑戦性障害はDSM-5(米国精神医学会の診断基準)で以下のように定義されています。
A. 反抗的・挑戦的な行動パターン(6か月以上)
以下のうち4項目以上が見られる:
●しばしばかんしゃくを起こす
●しばしば大人と口論する
●しばしば指示に従わない・拒否する
●わざと他人を苛立たせる
●自分の失敗や問題を他人のせいにする
●神経過敏で簡単にイライラする
●怒りや恨みの感情を持ちやすい
●執念深い態度が6か月以内に2回以上ある
B. 社会・学業・家庭生活における機能障害
症状が家庭、学校、友人関係などで明確な支障を引き起こしている。
C. 他の精神障害では説明できない
うつ病や双極性障害のエピソード中のみ見られるものではない。
反抗挑戦性障害はなぜ起きるのか(要因)
反抗挑戦性障害は単一の原因ではなく、複数の要因が関係します。
①生物学的要因:感情反応が強く、自己制御が苦手な子ども
生まれつき「感情のスイッチが入りやすい」子がいます。ちょっと注意されただけで泣いたり怒ったり、興奮すると止まらなくなったりするのは、気質的な特徴の一つです。これは親のしつけが悪いわけではなく、生まれ持った「神経の敏感さ」に関係しています。
● 兄弟で同じように注意しても、上の子はすぐに「わかった」と切り替えるのに、下の子は泣き叫んでしばらく立ち直れない。
● 予定の変更(「今日は公園じゃなくて買い物に行くよ」)に強い抵抗を示して、パニックになってしまう。
このような子は、感情を整えるためにより多くのサポートが必要です。親が落ち着いて寄り添うことで、少しずつ「気持ちの切り替え方」を学んでいくことができます。(後で具体的に説明します。)
②神経学的要因:前頭前野や扁桃体の調整機能の未成熟
脳には「気持ちを調整するブレーキ役」と「感情のアクセル役」があります。ブレーキ役は前頭前野、アクセル役は扁桃体です。反抗挑戦性障害の子どもは、このブレーキ(前頭前野)の働きがまだ未熟なため、怒りや不安のアクセルがかかると、止めるのが難しいのです。
● 兄弟げんかで「もうやめなさい」と言われても、怒りが収まらず手が出てしまう。
● 幼稚園でお友達におもちゃを取られたとき、すぐに叩いてしまう。
これは「わがまま」ではなく、脳の発達途中の自然な姿です。トレーニングや関わり方次第で、前頭前野は少しずつ育ち、「待てる」「落ち着ける」力が伸びていきます。
③遺伝的影響:衝動性や感情調整の困難さが家族内に見られる
研究では、衝動性や感情のコントロールのしにくさが遺伝的に影響することが分かっています。例えば、「親も子どものころ感情的だった」「親自身が今もイライラしやすい」といったケースは珍しくありません。
● 親も子どものころ、先生や親に「頑固」「すぐカッとなる」と言われていた。
● 親が忙しくてイライラしていると、子どもも敏感に反応して、怒りっぽくなる。
これは「親のせい」という意味ではなく、気質が似ていることでサポートが必要なポイントも似ているということです。ですので、親が自分自身のイライラを落ち着ける方法を学ぶと、子どもも自然にその影響を受けて落ち着きやすくなります。
④心理的要因
自己効力感の低下
反抗挑戦性障害の子どもは、「自分はダメだ」「どうせうまくいかない」といった気持ちを持ちやすい傾向があります。これは生まれつきの気質だけでなく、日常生活で「叱られることが多い」「うまくいかない経験が積み重なる」ことで、少しずつ自己効力感が下がってしまうためです。
● 何かに挑戦してもうまくいかず、「どうせできない」と投げ出してしまう。
● 親や先生に繰り返し注意され、「自分は悪い子なんだ」と感じてしまう。
● できたことより、できなかったことにばかり目が向き、自信をなくしていく。
このように、自信を失くしてしまうと「どうせ怒られるなら反抗したほうがいい」という防衛的な態度につながることもあります。親が子どもの傷つきに気づいてあげること、子どものことをよく観察して小さなことにも承認メッセージを送ること、成功失敗に関係なくチャレンジしようとする気持ちを認めることが大切です。
不適切なコーピング(ストレス対処スキルの不足)
コーピングとは、ストレスに対処する力のことです。反抗挑戦性障害の子どもは、このスキルがまだ未発達なため、困ったときに「泣く」「怒る」「反抗する」以外の方法を知りません。
● 友達におもちゃを取られると、「返して!」と叫んで手が出てしまう。
● 苦手な課題に取り組むとき、「無理!」と投げ出して、机の下に隠れてしまう。
● 予定外のことが起きると、「やだ!」とパニックになってしまう。
これは「わがまま」ではなく、単に「別のやり方をまだ知らない」だけです。「イライラしたね」「悔しかったね」のように子どものストレスに寄り添って、子どもの気持ちが落ち着いたら、イライラした時の対処法や困った時の解決方法を考えることで、対処スキルを教えることができます。
⑤環境的要因
一貫性のない養育(厳しすぎる・甘やかしすぎる)
子どもは、日常の中で「大人の対応のパターン」を学びます。しかし、しつけが厳しすぎる家庭では、子どもが「何をしても怒られる」と感じやすく、反発や反抗で身を守ろうとします。逆に、甘やかしすぎて境界があいまいな家庭では、「どこまでやっていいのか」が分からず、結果として挑戦的な態度が強まることもあります。
● 昨日は叱られなかったのに、今日は同じことで怒られる
→子どもには何がルールかがわからず混乱するため、困惑から強く反発したり、癇癪を起こすことで自分を通そうとします。
● 厳しく罰ばかり与えられる
→ 「どうせ何をしてもダメ」と感じと反発や絶望から強い反抗的な態度をとります。
● 逆に、何をしても許される
→ 何でも許される状況は子どもを不安にします。
どこまでしたら叱られるかを知るために、わざと反抗的な態度を取ったり、感情を爆発させずにいられないのです。きつく叱る必要はなく、何をしてはいけないかの限界設定をしてあげる必要があります。
家庭内の葛藤やストレス(夫婦不和、虐待、ネグレクト)
家庭が安心できる場所でないと、子どもは常に「緊張モード」で過ごすことになります。夫婦げんかが絶えなかったり、言葉や態度で傷つけられる経験があると、子どもは「どうせ誰も守ってくれない」と感じ、反抗や挑戦的な態度で不安を隠そうとします。
● 家で大人の怒鳴り声が絶えない → 学校でも先生に反抗的な態度を取る。
● 親が子どもに無関心 → 注意を引くためにわざと反発する。
● 虐待やネグレクト → 「安心して甘える」という体験がなく、警戒心が強くなる。
学校でのいじめや不適応
学校で安心できない経験が続くと、子どもは「どうせ自分は嫌われている」「守ってもらえない」と感じ、家庭でも攻撃的な態度を見せることがあります。
● いじめられているが、うまく言葉で助けを求められない → 家で爆発する。
● 勉強についていけず、毎日ストレス → 困り感やストレスが怒りの爆発となって現れる。
● 友達とのトラブル → 余裕がなくなり、些細なことでも怒りやすくなる。
⑥ADHDなど発達特性との併発
反抗挑戦性障害は、ADHD(注意欠如・多動症)などの発達特性を持つ子どもに併発することもよくあります。衝動的に行動してしまったり、感情を抑えるのが苦手なため、結果として反抗的な態度が強まるのです。
● ADHDで衝動的に動いてしまい、注意を受ける
→ 自分が困っていることをわかってもらえない怒りや絶望、反発から、反抗的になる。
● 集中が続かず、繰り返し叱られて自信をなくす
→ 怒りで反抗することで自己防衛する。
このように、反抗挑戦性障害はわがままではなく、子どもが置かれた環境や経験によって強まることがあります。安心できる家庭環境や一貫した対応、そして学校や発達特性への理解が整うことで、子どもの反抗的な行動は少しずつ減っていきます。
反抗挑戦性障害の治療
反抗挑戦性障害は早期介入が非常に重要です。治療は多面的に行われます。
① 行動療法
● ペアレント・トレーニング:親が一貫したルール設定や肯定的強化法(褒める・望ましい行動を増やす)を学ぶ
● トークンエコノミー法:望ましい行動にポイントを与えて強化する
② 認知行動療法(CBT)
● 子ども自身に「怒りのコントロール」「問題解決スキル」を教える
● 衝動的な思考や「不公平だ!」という認知を修正する
③ 家族療法
● 家族間のコミュニケーション改善
● 親子関係の信頼回復
④ 薬物療法(必要な場合のみ)
● ADHDなど併存障害がある場合に医師の診断と処方のもと薬物を使用することがある
反抗挑戦性障害:本人にできること
反抗挑戦性障害の子どもにとって、感情をコントロールし、安心できる行動のパターンを少しずつ身につけることはとても大切です。これらは、単なる「しつけ」ではなく、自分で自分を整えられる力(自己効力感)や「自分はできる」という自尊心を回復するための基盤になります。
①深呼吸やクールダウン法の練習
イライラや怒りで頭がいっぱいになると、考える力が働かなくなります。深呼吸やクールダウン法(その場を離れる、静かな場所で休むなど)を繰り返し練習することで、神経が落ち着きやすくなり、気持ちをコントロールできる感覚が育ちます。
→ 「落ち着けば大丈夫」と自分で実感できると、自信が回復していきます。
②困ったときに大人に助けを求める
「困ったら人に頼っていい」と学ぶことは、安心して生きるための大切なスキルです。助けを求めて受け入れてもらう経験は、「自分は一人じゃない」という感覚を育て、反抗や攻撃で身を守らなくてもよい状態をつくります。
→ これが、信頼感と自尊心の回復につながります。
③小さな成功体験を積む
大きな目標よりも、「できた!」を積み重ねることが大切です。たとえば、今日は10分間落ち着いて宿題ができた、イライラしても1回深呼吸できた…そんな小さな成功を親と一緒に確認すると、子どもは「自分にもできるんだ」と感じられるようになります。
→ これが自己効力感の育成につながります。
④「やめる → 考える → 行動」のステップ練習
イライラしたとき、すぐに行動に移るのではなく、「一度止まる」「考える」「行動する」というステップを繰り返し練習します。これは、感情と行動の間に「考える時間」を入れるためのトレーニングです。
→ 「感情に振り回されずに行動できた」という経験が、子どもの自信を支えます。
これらのスキルは、単なる問題行動の対処法ではなく、「自分をコントロールできる」という感覚を取り戻し、自己効力感と自尊心を回復させるために不可欠な力です。親が見守りながら一緒に練習していくことで、子どもは「できる自分」を実感できるようになります。
反抗挑戦性障害:家族にできること
反抗挑戦性障害の子どもにとって、家庭の対応は「安全基地」の役割を果たします。感情的にぶつかるのではなく、安定した対応を積み重ねることで、子どもの自律神経が整いやすくなり、自己肯定感や自信が回復していきます。
①一貫性ある対応
「してもよいこと」と「してはいけないこと」をシンプルに明確に決めて伝えます。例えば、「イライラした時に人を叩いてはいけないが、クッションを叩いてもいい」というように。
②小さな「できた!」を褒める
イライラした時に「イライラしている」と人に伝えられたり、深呼吸をしたり、別の部屋に行くなどの行動が取れたら「やったね!」と褒めます。うまくできなかった時も、「やろうとしたね」「ここはできたね」のように良いところを見つけて褒めることが大切です。
子どもをよく見ていないとできないことですが、子どもは、大人が関心を持って自分を見ていてくれることで落ち着きを取り戻すことができるものですから、ぜひ、やってみてください。
③親が落ち着いて接する
子どもが癇癪を起こしたときに親が怒鳴ると、子どもの交感神経はさらに過覚醒になります。反対に、親が深呼吸して穏やかに寄り添うと、子どもの腹側迷走神経(安心の神経)が働きやすくなり、親の態度に影響を受けて落ち着くことができます。
④支援を求める
家庭だけで抱え込まず、スクールカウンセラーや地域の教育相談センター、医療機関、カウンセリングルームなどの専門家に相談することも重要です。親がサポートを得ることで余裕が生まれ、安定した対応ができるようになります。それが結果的に、子どもの安心にもつながります。
反抗挑戦性障害:カウンセリングでできること
①原因を整理し、理解を深める
反抗挑戦性障害がなぜ起きているのかを、お子さん一人ひとりのケースに基づいてわかりやすく説明します。
理由が整理できると、「どう関わればいいか」が自然と見えてきます。
②親子の自律神経を整えるサポート
反抗挑戦性障害のお子さんの特徴のひとつに自律神経の乱れがあります。子どもの自律神経を整えること(場合によっては親子で整えること)が、反抗挑戦性障害からの回復の大切な柱になることが多いです。
はこにわサロンでは、ポリヴェーガル理論に基づき、親子それぞれの自律神経を落ち着けるための方法(呼吸・声かけ・環境づくりなど)を実践的にお伝えし、セッションの中で一緒に練習していきます。
反抗挑戦性障害のお子さんは、感情が高ぶると「戦う・逃げる」の神経(交感神経)や、無気力になる「シャットダウン」の神経(背側迷走神経)に偏りやすく、落ち着きを取り戻しにくい状態にあります。親が落ち着いて寄り添うことで、子どもの神経は安心モード(腹側迷走神経)に切り替わりやすくなります。
この「安心の神経」が働くと、子どもは少しずつ感情を調整できるようになり、親も「イライラしてつい叱ってしまう」状態から抜け出しやすくなります。親子で一緒に自律神経を整えていくことが、感情の悪循環を断ち切る一番の近道です。
③子どもの気持ちを安全に表現できる場
箱庭療法や絵画療法などを通して、お子さんが言葉では表しきれないストレスや気持ちを外に出し、整理できるようサポートします。また、安心できる環境のもと、お子さんの気持ちを話せるカウンセリングの場も提供します。
④家庭での具体的な対応を一緒に考える
日常の中で使える対応方法を一緒に検討し、うまくいくまで伴走します。小さな変化を積み重ねることで、親子ともに「できる」という実感を持てるようになります。
⑤学校との連携支援
必要に応じて、学校への説明や協力体制づくりのポイントを整理します。先生との連携方法を考えることで、家庭だけで抱え込まないサポート体制を整えます。
反抗挑戦性障害:まとめ
反抗挑戦性障害は「わがまま」ではなく、神経や環境、気質の影響による「助けを求めるサイン」です。親が落ち着いて関わることで、子どもは安心し、自分を整える力を少しずつ育てられます。はこにわサロンでは、原因の整理から親子の自律神経サポート、家庭での対応まで一緒に取り組みます。ひとりで抱え込まず、回復の一歩を一緒に踏み出しましょう。