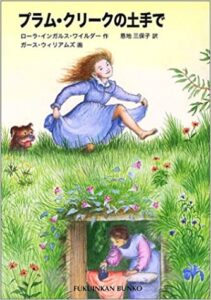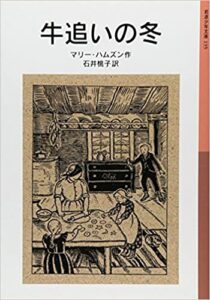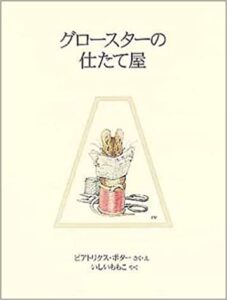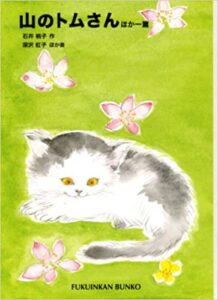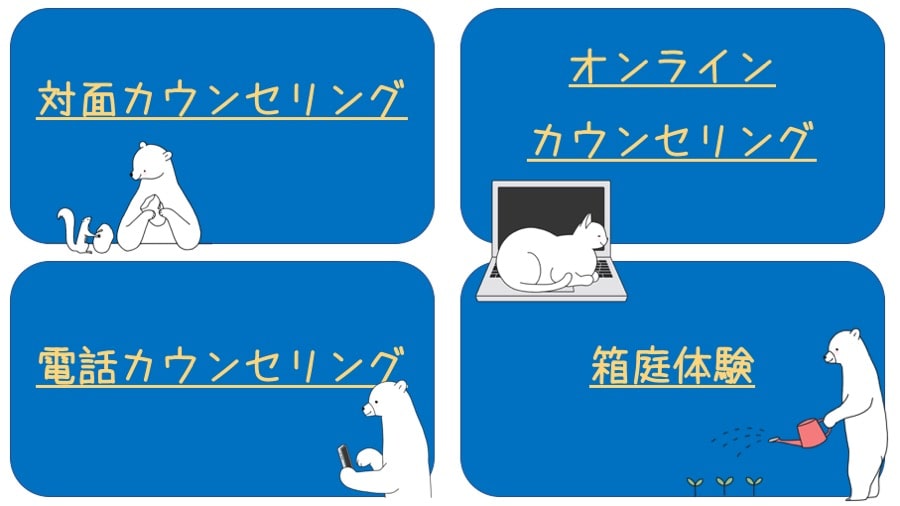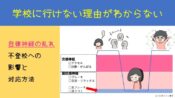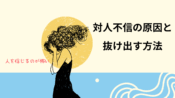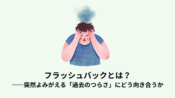「サンタクロースは本当にいるの?」と聞かれたら~サンタの卒業

東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田(臨床心理士・公認心理士)です(オンラインカウンセリング・電話カウンセリング受付中)
今年も残すところひと月を切りましたね。
大人はとっても慌ただしいこの季節、子どもたちはクリスマスに冬休みにお正月と楽しいことが間近に迫ってわくわくしているのではないでしょうか。
でも、小学生のご家庭では「サンタクロースはいつまで?」と頭を悩ませているかもしれません。

わたし自身、子どもが小学生になってからは毎年「子どもはまだサンタクロースを信じているかしら?」「いったいいつまでサンタクロースが来たらいいのか?」と気を揉んでいました。
学校で「サンタクロースは親なんだってよ」と初めて聞いてきたのは確か小2のときですが、まだ周りに「いるから」と思ってくれているお友だちもいたせいか、そう疑うこともなくサンタクロースが到来。
でも、翌年からは、サンタクロースへの手紙をフィンランドに送るプロセスを子どもにしてもらい、リアリティを演出しました。(ポストインする前に中を見るのがひと苦労!)
5年生になると、あえて「サンタクロース」とは言わずに「欲しいものがある」と言ってきましたが、ツリーの下にプレゼントを置きました。
ここまで粘ったのでもういいか、と6年生で「今年はサンタクロースは来ないけれど、欲しいものがあったら相談しようね」と伝えたところ、すごくがっかりした顔をされてしまいました。わかってはいたけど、親の口から聞くのは「本当に残念!」という感じが伝わってきました。
このように、わたし自身は6年間悩み続けた挙句に、なんだかしょんぼりしたカミングアウトになってしまいました。
どうしていたらよかったのかなぁと今なお悩み続けているんです(笑)
ですから、同じように悩んでいるお父さん・お母さんたちに何かヒントになればと、これまで考えてきたことについて書いてみたいと思います。
せっかく親子で大切にしてきたサンタクロースですから、子どものこころに納まる卒業ができるといいですね。
子どもたちにとってのサンタクロース
子どもたちにとって、サンタクロース体験にはどんな意味があるでしょうか?
②わくわくしながらサンタクロースを待つこと
③サンタクロースを通じて、自分がこの世界のなかで愛され認められていると感じること
もし、親が直接この役割を果たしたら、子どもたちはどう感じるでしょうか。
プレゼントを買ってもらえたり、おいしいごはんを一緒に食べるイベントはとても楽しくこころに残ると思いますから、これもまたよい体験になるでしょう。
けれども、やはり広がりや奥行きが狭まってしまうように、わたしには感じられます。

子どもたちがサンタクロースを通じて、会ったことのない相手を想像したり、何か親・現実を超えるよい存在にこころを向けると温かい気持ちになるという体験をしたり、何よりまだ見ぬ誰かから既に愛されているという体験をするのは、サンタクロースという存在あってのことではないかと思うからです。
年齢を重ね、小学生になると、必ずといっていいほど誰か「知ったかぶりさん」が「サンタクロースなんていないよ!本当は親だよ!」という爆弾発言をします。
でも、多くの子どもたちは、真実を知っても、誰に言われなくても、年下の者たちがサンタクロースを信じることに協力します。
年上の子どもたちのこうした行動は、サンタクロースを信じる体験がとても貴重であることを知っているからなのではないでしょうか。

サンタクロースが親だとわかる頃の子どもたちの心理とは?
サンタクロースが親だ、とバレてしまうのは、いつ頃が多いのでしょう?
個人差(所属する集団の差?)はありますが、小学校3年生ごろが多いでしょうか。
この小学3年生の頃、というのは、子どもの成長過程としては、なかなかに難しい時期の始まりです。
「前思春期」といって、思春期の前段階ですが、子どもによっては思春期以上にむずかしくなることもある時期です。
何がおきるかというと、心理的な親離れが始まります。
それまで何があってもお父さん・お母さんがいてくれたら、「大丈夫だよ」と言ってくれたら、不安は払しょくできていたのですが、前思春期に入ると「本当かな?」という疑問が湧いてきます。
幼少期からいつも「全知全能」だと思っていた親が、欠点や限界もある「人」だとわかるようになってくるのです。
それは、子どもにとってはなかなか怖いことです。
折しも、このころは、子どもたちが「死」に関心が芽生える頃でもあります。
「死ぬってどういうことなの?」「死んだらどうなるの?」「もし自分が死んじゃったら?」「もしお父さんやお母さんが死んじゃったら!?」答えの出ない問いに悩み、怖くなってしまったときに、お父さん・お母さんが「大丈夫」と安心させてくれたらどんなにいいか!(でも、もう、それだけじゃあ、安心できない!)
このような時期こそ、サンタクロースの存在が子どもたちのこころを温めてくれたらいいのですが。
ほんとうにタイミングが悪いとしか言いようがありません。
でも、こんな風に子どもたちが不安になりやすい時期だからこそ、サンタクロースが「親だった、残念」で終わらせないで、子どもがサンタクロース体験を糧にできるような閉じ方をしてあげたいと思うのです。
これが、わたしが「サンタクロースの閉じ方」に長い間こだわっている理由です。
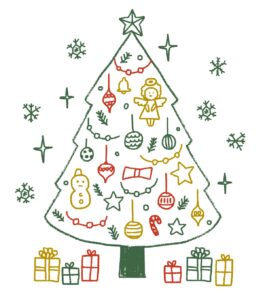
サンタクロースから卒業するとき
サンタクロースは親だったとわかると、子どもはとてもがっかりします。
あんまりがっかりしたものだから「だまされた!」なんて強い言葉を使う子どももいます。
でも、もし子どもがそんな言葉を使ったとしても、大人を非難しているのではなく、落胆からくる怒りの表現であると受けとめてあげられるといいなと思います。
サンタクロースが親だとバレて、親もきっとあきらめや寂しさを感じているのではないでしょうか。
そんな時は、親がサンタクロース役を果たしながら自分たちも心躍るクリスマスを過ごしてきたことや、これまでの楽しかったクリスマスの思い出などを子どもと分かち合えるといいなと思います。
そして、大切な人のことを思ってプレゼントを準備する楽しみ、当日まで秘密にするスリル、プレゼントを交換してしあわせな気持ちになる体験などを、サンタクロースなしでも続けていく工夫を相談してみて欲しいと思います。
こんどは親子で、見知らぬ誰かのサンタクロースになる、ということもできるかもしれませんね。
正解はないけれど、我が家の「サンタクロースの卒業」をどうぞ大切にしてみてくださいね。

クリスマスを考えるおすすめ本
最後に、いろいろなクリスマスを体験できる本をご紹介します。
サンタクロースを閉じるお子さんと一緒に楽しんでもよいかもしれません。
『サンタクロースの部屋 子どもと本をめぐって』松岡享子
東京子ども図書館を設立し、子どもの本の翻訳や創作を手がけられた松岡享子さんが、子どもがサンタクロースを信じることや、それを大人が守ることの意義についてお話されています。
『プラム・クリークの土手で』ローラ・インガルス・ワイルダー
『大草原の小さな家』でおなじみのこのシリーズ。
大草原で暮らすローラのところには、毎年サンタクロースがプレゼントを届けにきていて、それをローラはとても楽しみにしていました。
けれど、苦労して育てた農作物をイナゴに食べられてしまった年。
かあさんは、ローラに「今年のクリスマスは、とうさんのために馬を買いましょう」と言うのです。
困惑するローラに、かあさんは「もう、あなたたちはわかってもいい年齢だと思いますよ」と諭します。
今年、うちには、クリスマスのプレゼントを買う余裕がないのです。お金は、家族が生きていくために使わないといけないのです。
ローラは「はい、かあさん」と同意しながら、内心とてもがっかりします。
さて、クリスマスはつまらなかったでしょうか?
いいえ。
とうさんの喜ぶ顔。
家族の幸せがプレゼントだとローラが体験する初めてのクリスマスになりました。
『牛追いの冬』マリー・ハムズン
北欧の農家の子どもたちのお話です。
4人兄弟の長男オーラ(11歳)は、ある秋の日に街の雑貨屋さんにいました。
夏の間、牛追いの手伝いをして獲得したお金を持っていたので、なんだか少し大人になった気持ちで、好きなものを買えるワクワクした気持ちで、ぶらりと立ち寄ったのです。
すると店頭には、オーラがすぐにでも手に入れたい面白そうな本が入荷していました。(オーラは読書家なんです。)
でもね。ちょっと見栄もあって、自分の欲しい本ではなく、お父さんとお母さんにあげるクリスマスプレゼントを買ってしまうんですよ。
帰り道、オーラは、後悔します。きっとあの本はすぐに売り切れてしまうだろうな。やっぱり自分の欲しいものを買っておけばよかったな。
でも、初めて自分でプレゼントを買った誇りも感じていました(早速、弟に自慢してます)。
さて。
小さな家の中。子どもたちの様子に気づいたお父さん・お母さんは、ちゃんとオーラの欲しかった本をクリスマスプレゼントにしてくれたんですよ。(よかった!)
オーラの、この初体験(ちょっと背伸びのクリスマス体験)は、オーラをひとつ大人にしたことでしょうね。
『グロースターの仕立て屋』ビアトリクス・ポター
ある老齢の仕立て屋がやり残した仕事を、ネズミたちが仕上げてくれます。
ボタンひとつ残して。
「糸が足りぬ」とメッセージがありました。
仕立て屋はどんなに驚いたことでしょう!
不思議な、何か大きな愛情に包まれている感覚だったことでしょうね!
この物語、ネズミではなく、人間がこっそり仕上げておいてあげたというお話がもとになっているといいます。
プレゼントは、高価な物でなくても構わない。でも、愛情とサプライズは大事ってことですね。
『山のトムさん』石井桃子
クリスマスって、家の中に秘密が増えませんか?
こっそりと、プレゼントを準備する。
何が欲しいのか、探りを入れたり、入手の手はずを整えたり。
買ったり、作ったり、包んだり。
できたら、隠す!
見つからないように・・・注意を要する。
とにかく、忙しいけど、わくわくする忙しさです。
『山のトムさん』は、石井桃子さんの実体験に基づくお話だと思いますが、北国で過ごすある「家族」の、戦後の物のない時代に、知恵と工夫で贈り物をしあうにぎやかで晴れやかなクリスマスの模様が描かれています。
日々の労働が忙しく、手袋が片っぽしか編み上がっていなかったり。
プレゼントのあてがなくて困っていたら、クリスマスのご馳走を仕留められたり。
こんな風に、みんなが少しずつ知恵と工夫を寄せ合って、楽しいクリスマスが過ごせたら、どんなにいいことでしょう!
まとめ
「サンタクロースは本当にいるの?」と聞かれて困ったら、親はどうしてあげたらよいのか。
正解はないけれども、子どものサンタクロース体験を守りながら、新しい我が家のクリスマスを見つけていってくださることをこころから願っています。
では、どうぞみなさま、メリークリスマス!