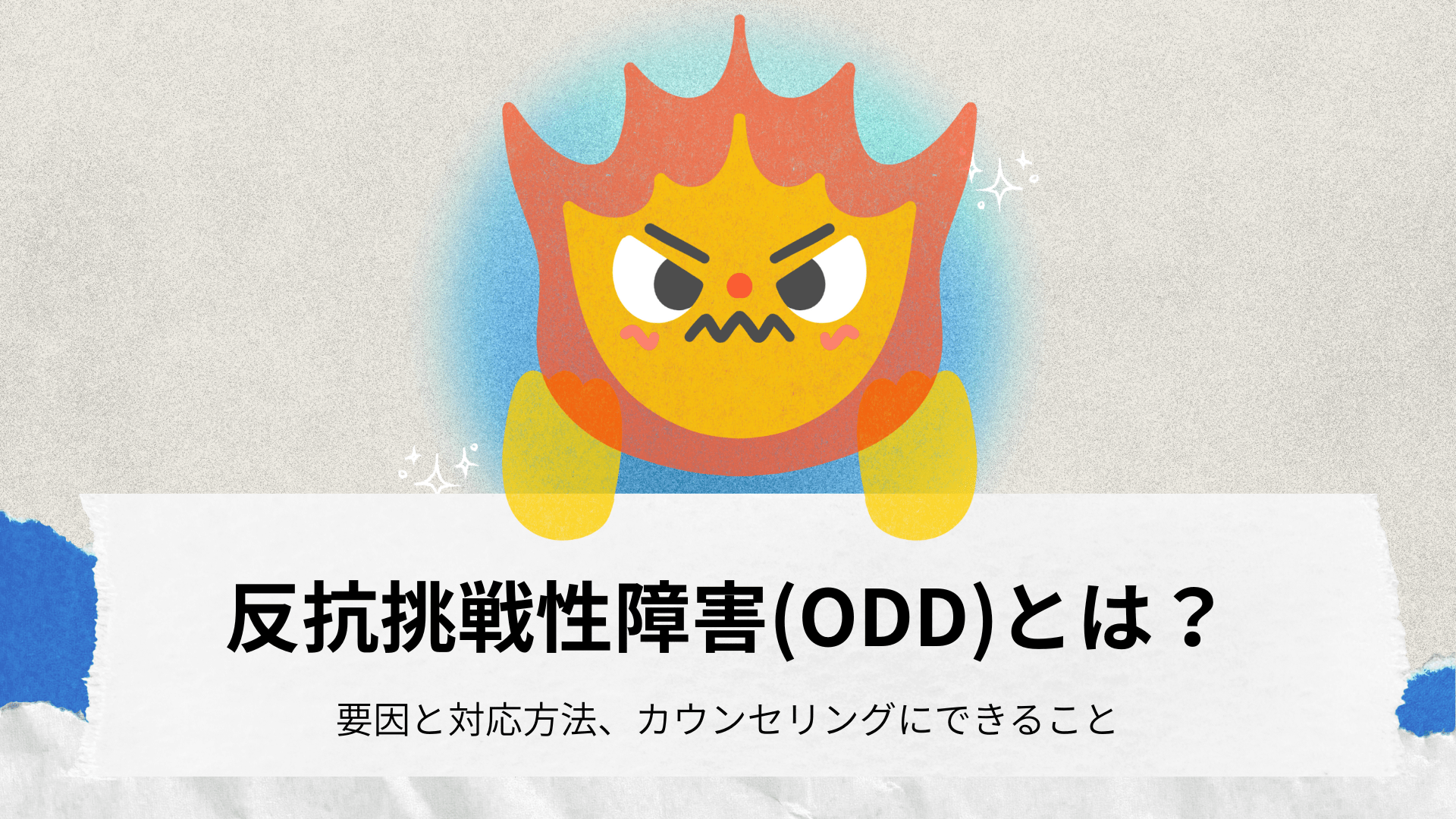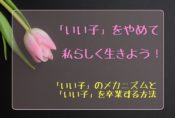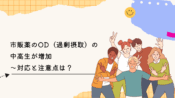PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは?回復する方法は?
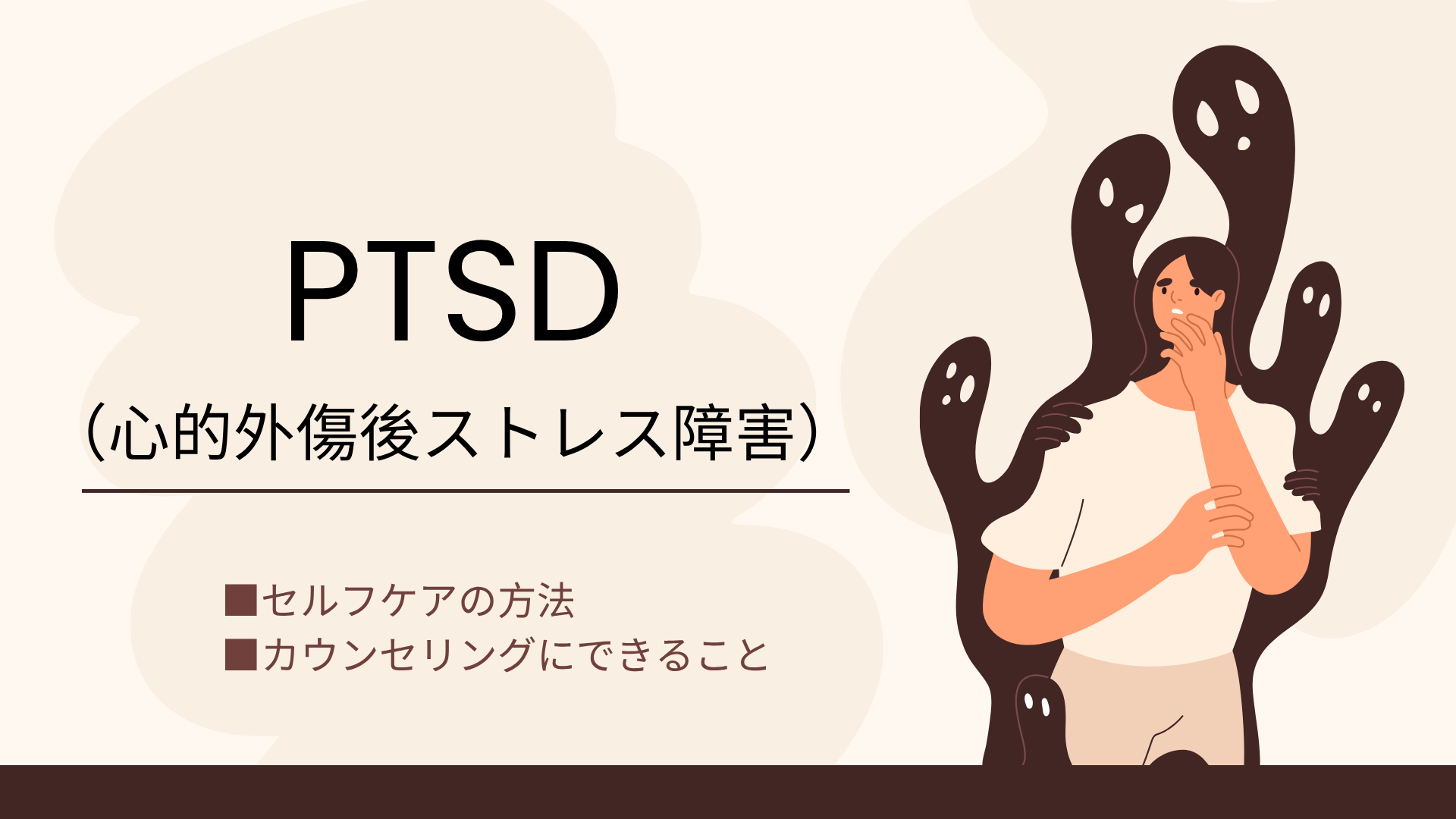
東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田(臨床心理士・公認心理師)です。
PTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)とは、命の危険や強い恐怖・無力感を伴う出来事を経験したあと、その記憶が心や身体に深く刻まれ、日常生活に支障が出る状態です。
この記事では、PTSDとは何か、なぜ起きるのか、どんなつらさがあるのか、ケアや回復の方法についてわかりやすくお話します。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは?
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、強い恐怖や無力感を伴う出来事を経験したあと、その記憶や感覚が心や身体に残り、日常生活に影響を及ぼす状態です。
例えば:
● 交通事故のあと、車に乗ろうとすると動悸がして手が震えてしまう
● 地震や災害を経験したあと、小さな揺れや警報音でも過剰に反応して眠れなくなる
● 子どもの頃に虐待を受けた経験から、今も大きな物音や怒鳴り声を聞くと身体が固まってしまう
● いじめを受けた記憶がよみがえり、人前で話そうとすると強い不安で声が出なくなる
これらは決して「気の持ちよう」や「心が弱いから」ではありません。脳や自律神経が「危険から身を守るため」に過敏になってしまった結果、安全なはずの「今」でも身体が過去の危険を現実のように感じてしまうために起こります。
つまり、PTSDとは「過去の体験が、今この瞬間に影響を与え続けている」状態です。
適切な理解とサポートがあれば、この過剰な防衛反応を少しずつ和らげ、安心できる感覚を取り戻すことができます。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)の診断基準(DSM-5)
PTSDの診断基準は以下の通りです。
診断は医師(精神科医・心療内科医)が行います。
臨床心理士・公認心理師は、相談者にPTSDが疑われる場合に、医療機関の受診をお勧めすることがあります。
① 外傷体験
命の危険や深刻な心身の脅威となる出来事を
● 直接体験
● 目撃
● 近親者が被害に遭う
● その詳細を繰り返し知る、といった形で経験する。
② 侵入症状
トラウマ体験が繰り返しよみがえる。
● フラッシュバック
● 悪夢
● 強い心理的・身体的反応(動悸、発汗など)
③ 回避
● トラウマを思い出させる状況や場所、人、話題を避ける。
④ 否定的認知・感情
● 「自分はダメだ」という否定的な自己評価
● 感情の麻痺や無気力
● 喜びを感じられない
⑤ 過覚醒
● ささいな刺激に驚く
● 常に緊張している
● イライラ・怒りっぽさ
● 睡眠障害
⑥ 期間
症状が1カ月以上続く。
⑦ 機能障害
日常生活(家庭・学校・仕事・人間関係)に支障が出ている。
PTSDの治療方法
PTSDは早期の理解と対応で回復しやすいことが分かっています。主な治療は次の通りです。
心理療法
● トラウマ焦点療法(TF-CBT):安全な環境で少しずつトラウマに向き合い、恐怖記憶を整理
● EMDR:眼球運動を用いてトラウマ記憶の処理をサポート
● 身体志向アプローチ(ソマティック・エクスペリエンシングなど):身体の感覚を通じて神経系を落ち着ける
● ポリヴェーガル理論に基づく介入:呼吸法やセルフケアで自律神経を整える
薬物療法
● 医師の診断に基づき、不安や不眠などを軽減するお薬が処方されることがあります。
PTSD: 自分でできること
PTSD症状に対して、自分でもできることがいろいろありますから、ご紹介していきます。
フラッシュバック(過去の記憶がよみがえる)
映像や音、匂いなどで過去の出来事が急によみがえったり、心臓がドキドキする、身体が固まるなどの状態になることがあります。そのようなときできることには以下のようなものがあります。
● グラウンディング
五感を使って「今、ここ」に戻る方法です。例えば、「床に足の裏をしっかりつけて感覚を感じる」「部屋にある青い物を3つ探す」などを通じて、フラッシュバック(過去)から今ここに意識と感覚を戻します。
● 呼吸法
4秒吸って、6秒かけて吐く(長めに吐くと自律神経が落ち着く)。呼吸を通じて、自分の身体に意識を向けます。
● 安全確認の言葉
「今はもう安全」「ここはあの時とは違う場所」と自分に声をかける。自分と対話することができると、自己ケアがしやすくなります。
過覚醒(イライラ・過敏・眠れない)
PTSDの影響で、常に警戒していてリラックスできなかったり、小さな音や刺激に敏感に反応する、また、過緊張のため夜眠れない、などの影響が出ることがあります。そんな時の対処法には以下のようなものがあります。
● 刺激を減らす
部屋の明かりを調節する。
寝る1時間前はスマホやテレビをオフにし、部屋を暗く静かにする。
● 温熱リラックス
ぬるめのお風呂(38〜40℃)にゆっくり浸かる。
● 深い呼吸や軽いストレッチ
夜寝る前にゆっくり呼吸をしたり、軽いストレッチをして身体を緩めます。
回避(思い出すことを避ける)
PTSDの影響で、つらい出来事を思い出さないように、場所や人、話題を避けることがあります。これは、一時的には悪い方法ではありませんが、回避に頼りすぎると生活範囲がどんどん狭まってしまうという難点があります。
● 小さなステップで慣れる
人の少ない時間の外出からしてみる。
● 自分を責めない
今できないのは、自分が自分を守ろうとしている結果です。自分を責める必要はありません。無理のないチャレンジを検討してみましょう。
否定的な感情・思考
PTSDの影響から、「自分が悪い」「もう何も良くならない」と考えてしまったり、無力感や罪悪感に囚われてしまうことがよくあります。これも「自分のせい」ではなく、トラウマの影響と理解して、できることから始めてみましょう。
● 記録をつける
その日の出来事や思いを記録につけてみましょう。冷静に振り返ることができ、自己理解の糸口となります。
● セルフコンパッション
もし、困っている友だちがいたらなんと声をかけますか?
お友だちにするように、自分にもフェアで親切な態度をとれるように、少しずつ練習します。
身体症状(頭痛・胃痛・疲労)
PTSDの影響で、自律神経が乱れるため、肩こり・頭痛・胃の不調が出やすかったり、慢性的に疲れやだるさで動けない、ということが生じやすいです。
● 自律神経ケア
深呼吸、軽いウォーキング、ストレッチなど、身体をゆっくり動かして自律神経を整えましょう。
● 食事と睡眠を整える
生活リズムを整えることは、大事なセルフケアです。まずは、同じ時間に寝て起きることや、3食の食事を摂ることから始めてみてください。
● マッサージや温め
身体の凝りを温めると、緊張が緩み、自律神経も整いやすくなります。
これらは「トレーニング」と同じで、一度で劇的に変わるものではありません。小さなステップを積み重ねることで、神経が少しずつ「安心モード(腹側迷走神経)」を取り戻していきます。
PTSD: はこにわサロンのカウンセリング
当サロンでは、PTSDでお困りの方に、安心して回復の一歩を踏み出せるよう、以下のサポートを行っています。
トラウマ反応の理解
「なぜフラッシュバックが起きるのか」「どうして不安や緊張が続くのか」を、神経科学や心理学の視点からわかりやすく説明します。「心身からのSOSメッセージだった」「気のせいではなかった」と理解できることは、それだけで安心感を生みます。
安全な感情表現の場
PTSDでは、その出来事を詳しく話すことが必ずしも必要ではありません。無理に話そうとすると、かえってトラウマを再体験してしまう可能性があるためです。
はこにわサロンでは、「話してもいいし、話さなくてもいい」という姿勢を大切にしています。出来事そのものではなく、どんな時に困るのか、どんなふうに感じてつらいのかに焦点をあててお話を伺います。
また、言葉にしにくいときには、箱庭療法や絵画療法を使って、無理なく気持ちを外に出せるようサポートします。
日常の対応方法の検討
発作や不安が強くなったとき、「どうしたら落ち着けるのか」「何をすれば安心できるのか」を一緒に考えます。
例えば、
● 不安が強いときにできる「呼吸法」や「グラウンディング」
● 眠れない夜のためのセルフケア
● フラッシュバックが出たときの安全確保の方法
など、日常ですぐ使える具体的な方法を一緒に検討し、練習をサポートします。
自律神経を整えるサポート
PTSDのつらさの背景には、自律神経の乱れがあります。はこにわサロンでは、ポリヴェーガル理論に基づいて、呼吸法・セルフタッチ・安心できる環境作りなどを一緒に練習します。「怖い」と感じた神経を「安心モード」に切り替える体験を重ねることで、少しずつ心と身体が落ち着きやすくなります。
必要に応じた医療連携
症状が強く、医療機関でのサポートが必要な場合は、カウンセリングと併用できるよう、一緒に医療機関をお探しします。心理的なサポートと医学的な治療を組み合わせることで、より安心して回復を進められます。
PTSDは「一人でがんばる」必要はありません。はこにわサロンは、あなたが「安心できる場所」を取り戻し、自分の力で回復できるようになるまで、伴走します。
PTSD(心的外傷後ストレス障害): まとめ
PTSDは「時間が経てば自然に治るもの」ではなく、神経と心に深く刻まれた反応です。しかし、正しい理解とサポートで、必ず回復の道は開けます。
ひとりで苦しまず、どうぞ、カウンセリングにつながってください。臨床心理士・公認心理士であるカウンセラーが回復をお手伝いさせていただきます。
関連記事