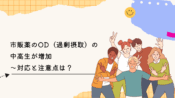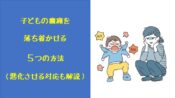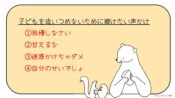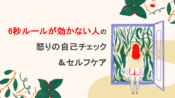6秒ルールが効かない人の怒りのセルフチェック&セルフケア
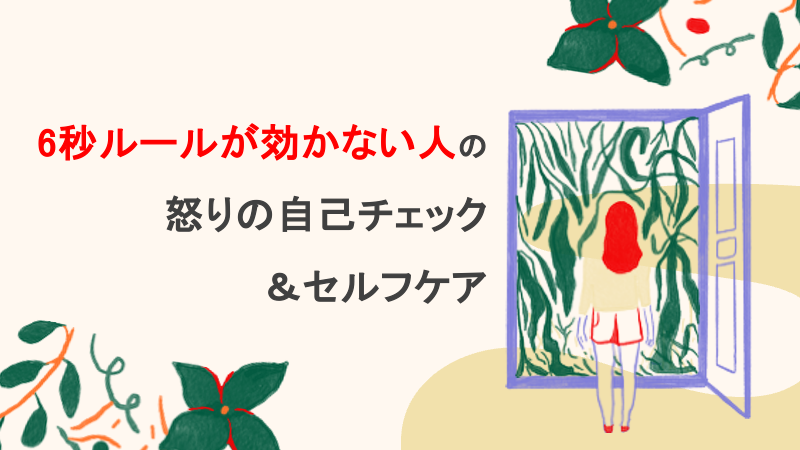
東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
「つい怒ってしまう」
「後で自己嫌悪になる」
「6秒ルールなんて無理」――そう感じたことがありますか?
怒りは悪い感情ではなく、自分を守るためのSOSなので、そのサインに気づき、怒りをコントロールしながらコミュニケーションができるとよいのです。
でも、いつもイライラして怒りっぽい方や、すぐに爆発しては後で後悔してしまう方は「なんでもいいから怒りをコントロールしたい!」と思っているかもしれません。
この記事では、「怒りがコントロールできずに悩む人のセルフチェックとケアのヒント」(今回)と「なぜ怒りが生じてしまうのか、どうすればコントロールできるのか」(次回)の2回構成で、怒りのメカニズムと解消方法にせまりたいと思います。
それでは、まず、あなたがどんな「怒りのパターン」を持っているのかをチェックしてみましょう。
怒りのセルフチェック
今のあなたに当てはまる項目に✔を入れてください。
①頭では冷静にしたいのに、体が勝手に反応してしまう
②怒ったあとに強い罪悪感や落ち込みを感じる
③子ども・部下・パートナーとよくぶつかる
④いつも緊張していて、気が休まらない
⑤「ちゃんとしなきゃ」と思うことが多い
⑥相手が言うことをきかないとイライラする
⑦「裏切られた」「軽く扱われた」と感じやすい
⑧人の期待に応えようとして無理をしてしまう
⑨本音を話せる相手が少ない
⑩怒る自分を嫌いだと思っている
✔の数が多いほど、「怒りを止められない状態」に近いサインです。
次のタイプ別診断で、今のあなたの怒りの強さを理解しましょう。
【0〜1個】安心ベースがある「リカバリー型」
イライラすることはあっても、落ち着きを取り戻せています。
自律神経が整っていて、人と安心してつながることができています。
怒りを感じた時は「疲れが溜まっているかな」「ストレスやプレッシャーが強かったかな」のように自分のコンディションを振り返ってください。
睡眠や休息がしっかり取れると、自分で怒りをコントロールすることができます。

【2〜4個】ストレス蓄積の「過覚醒型」
日常的に強いストレスやプレッシャーを受けていませんか?
常に気を張って交感神経が昂っているため、リラックスが難しくなっている可能性があります。
そのため、自分で怒りをコントロールしたいと思っても、頭より先に身体が先に反応しています。
そんなあなたに有効な心身のケアに呼吸法があります。
自律神経の乱れは怒りと深い関係性がありますが、自分でコントロールしやすいのは呼吸です。
10秒呼吸法がおすすめです。
1)まず息を吐き切って
2)「1、2、3」とゆっくり深く息を吸います
3)「4」で少し止めて
4)「5、6、7、8、9、10」で細く長く息を吐き切ります。
日常生活の中でちょっとゆるめたい時などに取り入れて、1日数回行うと効果的です。
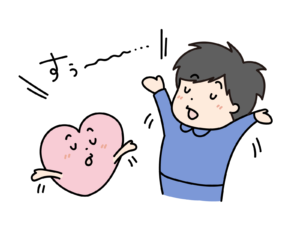
【5〜7個】「つながり不足」タイプ
あなたの怒りの裏には「わかってもらえない」「一人で頑張っている」という孤独感があります。
そのため、困っていても人に相談できず、ひとりで抱え込みがちになります。
「みんな頑張っているんだから弱音を吐いちゃダメ」などと抱え込まずに、誰かに相談してみませんか?
案外、ちゃんと受け止めて聞いてもらえるものですよ。
身近な人には話しにくい時は、カウンセリングもおすすめです。
セルフケアのおすすめは、熱い飲み物をフーフーして飲んだり、好きな香りのローションで手や身体をマッサージをすること。
ぜひ試してみてください。

【8〜10個】「防衛モード固定」タイプ
あなたの怒りの奥には、長期的なストレスや、過去の傷つき体験、慢性的なトラウマが隠されているようです。
不信感が強く、対人関係が苦手で、ハラスメントをしてしまう・ハラスメントを受けてしまいやすくなります。
また、自己肯定感が低く、いつも自分を責めてしまう、罪悪感を持ちやすいのではないでしょうか。
まずは、「怒りは悪いものではなく、自分を守ために大切な機能」と理解した上で、ご自分のケア(セルフケア)をするところから始めましょう。
先ほどご紹介した熱いものをフーフーして飲むことや10秒呼吸法のほかに、背中を預けてゆっくり座る、心地よいタオルケットにくるまるなどの方法、自然にふれる、生き物にふれることもおすすめです。
怒りが強すぎて日常生活に支障が出ている場合は、カウンセリングや医療機関の受診も検討してください。

では次に、チェックリストの項目ごとに、理解とケアの方法をご紹介していきます。
① 頭では冷静にしたいのに、身体が勝手に反応してしまう
怒りは思考よりも先に「神経の防衛反応」として起きます。
脳の扁桃体が危険を察知し、交感神経が一瞬で作動するため、身体が先に動いてしまうのです。
ですから、その反応を責めるより、「今、自分の神経が危険を感じたんだ」と気づくことが大切です。
心身が危険を察知して対応してくれたと理解して自分をねぎらえると、怒りを緩めることができます。
② 怒ったあとに強い罪悪感や落ち込みを感じる
怒った後に自分を責めるのは、冷静さを取り戻したから。
落ち込みは「関係を回復したい」という心の動きでもあります。
落ち着いてから、相手との修復(謝る・話す)をすると、関係性を深めることができます。
③ 子ども・部下・パートナーとよくぶつかる
人間関係の衝突は、「つながりの喪失=危険」と感じたときの神経反応です。
相手個人に対してではなく、期待が外れたと感じたときに怒りが起きます。
「なんで?」と相手を責めるより、「私は今、不安なんだ」と気づくことが大切です。
冷静さを取り戻したら、アイコンタクトや穏やかな声のトーンで関係継続の確認をしましょう。
④ いつも緊張していて、気が休まらない
慢性的なストレスやプレッシャーから、いつも気が昂っている過覚醒の状態です。
すると些細なことにも敏感に強く反応しやすくなります。
日常の中で「身体を預ける」時間を作りましょう。
ソファにもたれる、湯船に入る、毛布にくるまるなど、「安全」を身体で感じる練習を。
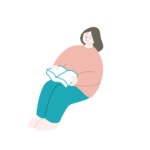
⑤ 「ちゃんとしなきゃ」「失敗できない」と思う
完璧主義は、「評価されないと危険」という無意識の学習から生じた自律神経の緊張です。
出来栄えに関わらず、よい日も悪い日も、「それでいい」と自分を肯定する力(自己肯定感)を育てていく必要があります。
まずは、1日1つ「手抜きOKポイント」を作ってみると「手を抜いても大丈夫」を体験できます。
⑥ 相手が言うことを聞かないと強いストレスを感じる
「相手をコントロールしたい」気持ちは、裏を返せば「自分の安全を守りたい」ということ。
まずは落ち着いて深呼吸し、相手ではなく自分の身体を整えましょう。
いったん離れて空を見る、遠くの音を聞く、熱いお茶を飲むのもおすすめです。
冷静さを取り戻すと、共感や協調する余裕が戻ってきます。

⑦ 「裏切られた」「軽く扱われた」と感じやすい
過去の「つながりを失った」経験が、心身に記憶されていて、似た状況になると、当時の防衛反応(怒り・悲しみ)が再び起きやすいのです。
「これは昔の痛みも関係してるかも」と気づくこと。
目をぎゅっとつぶって開くを繰り返すことや、バタフライハグ(手を胸のところで交差して、両肩のあたりを優しくパタパタ叩く)などのセルフケアをしてください。
そして、自分は自分を大切にしている、決して裏切ったりしないことを確認してみてください。
自分だけで回復するのが難しいことも多いので、カウンセリングも検討してみてください。
⑧ 人の期待に応えようとして無理をしてしまう
常に他者の反応や評価を気にしているのは、社会的防衛モードになっているから。
ストレスやプレッシャーでいつも不安で緊張していませんか?
もし、「いつも」「どんな人からも」認められないといけない、と感じていたら、それはやりすぎです。
いつも呼吸が浅い、夜寝付けないなどの症状も出ていると思います。
「相手がどう思うかは相手の仕事で自分の仕事じゃない」ことを確認してください。
また、安心して人と繋がれるリフレッシュやリラックス(例えばカラオケやスポーツなど)がおすすめです。
⑨ 本音を話せる相手がいない
人間は社会的な動物であるため、安心感を持って話せる人がいないと、自律神経が乱れて心身の不調を引き起こします。
安心してつながれる相手を見つけて、つながりましょう。
雑談や推し活でつながるのもGOODです。
身近に安心して話せる人がいないときは、カウンセリングも選択肢。
それもハードルが高い時は、自然に癒される体験や、動物に触れて安心する時間を持つところから始めてください。

⑩ 怒る自分を嫌いだと思っている
怒りを「悪いもの」と思いすぎると、抑圧と爆発を繰り返してしまいます。
怒りは「助けてほしい」「分かってほしい」という内なるSOS。怒りを敵ではなくメッセージとして扱う練習をしてみてください。
「わたしは何に傷ついたんだろう?」「何を守りたかったんだろう?」と自分に問いかけてみてください。
自分の中で納得できる答えを見つけられることが第一歩。
それを相手に穏やかに伝えられるようになると、怒りが健全な主張に変化していきます。
まとめ:怒りを抑えるより「安全」を取り戻す
6秒ルールが効かないのは、あなたの意志が弱いからではありません。
それは、脳と身体が「今は危険だ」と感じているから。
怒りを無理に抑えこむ前に、「今わたしは、自分を守ろうとしているんだ」と考えてみてください。
この一瞬の気づきが、怒りに穏やかなブレーキをかけます。また、怒りが湧いた時にひとまず一度、呼吸法などここまでご紹介してきた怒りの緩和方法をやってみてください。
このような試みが怒りに穏やかなブレーキをかけることができると、6秒ルールが機能するようになっていきます。
ただ、怒りのセルフチェックで4個以上チェックがついた方は、ご自分だけで怒りをコントロールできるようになるのは難しいことも多いです。怒りには心身や過去の自分からのSOSメッセージが託されているために頻繁に繰り返している場合があるからです。そんな時は、カウンセリングにつながることも検討してください。
次の「6秒ルール」が効かない理由と怒りを自分でコントロールする方法では、もっと詳しく怒りのメカニズムを紐解きます。
怒りを感じた時に、ご自分に何が起きているのかが理解できると、ご紹介してきた対応方法をもっと効果的に行うことができますし、自分に適した改善方法を見つけられるようになりますから、ぜひ、合わせて読んでください。