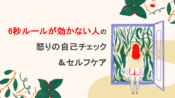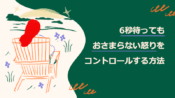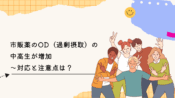「6秒待ってもおさまらない怒り」をコントロールする方法
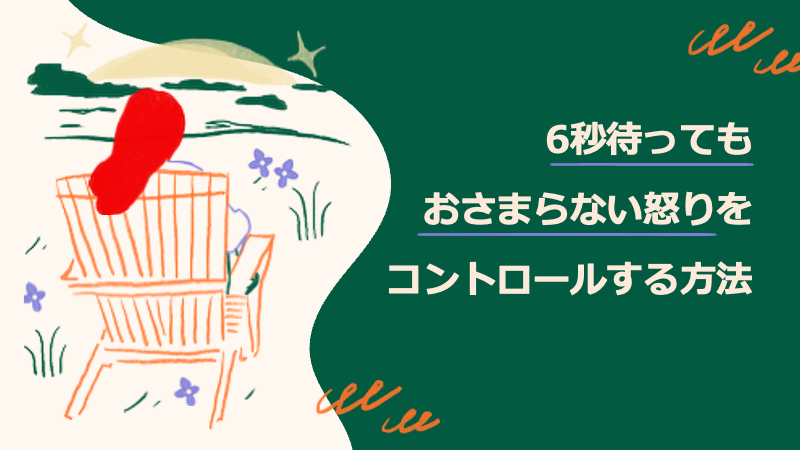
東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
アンガーマネジメントの基本としてよく知られているのが「6秒ルール」。
「怒りのピークは6秒間。この6秒をやり過ごせば冷静さを取り戻せる」といわれます。
確かに、ちょっとした苛立ちや小さなすれ違いなら、深呼吸をして6秒待つだけで落ち着けることもあります。
でも、怒りに悩む人ほど「6秒待っても怒りは収まらない」「気づいたら声を荒げていた」「むしろ怒りが増して逆効果だった」という経験をしているのではないでしょうか。
ではなぜ、「6秒ルール」が効かないことがあるのでしょうか?
どうすれば6秒で怒りのピークを収めることができるようになるのでしょうか?
その答えは、脳と自律神経のしくみ(ポリヴェーガル理論)にあります。
「6秒待つ」より早く起きる身体の反応
怒りが湧く瞬間、私たちの脳の中にある扁桃体(へんとうたい)が危険や脅威を検知します。
すると、思考や判断をつかさどる前頭前野(ぜんとうぜんや)が考えるよりも先に、交感神経が作動して心拍数や血圧を上げ、筋肉を緊張させます。
この反応は、わずか0.5秒以内に起きるといわれています。
つまり、理性が「待て」と言うよりも先に、神経が「戦え!」と命令しているのです。
これが、「6秒ルールが効かない」理由です。
つまり、怒りを抑えられないのは意志が弱いからではなく、神経が身を守ろうとしているからなのです。
言い換えれば、わたしたちは「怒っている」のではなく、「自分を守っている」のです。
闘争・逃走反応とは?
この神経の反応は闘争逃走反応と呼ばれます。
これは、人が危険や強いストレスに直面したとき、交感神経が瞬時に「闘うか逃げるか」を判断し、身体を動かすための防衛メカニズムです。
もともとは、狩りをして生きていた時代に、突然猛獣に遭ったとき「闘うか、逃げるか」を即座に決めて命を守るために働いていた反応です。
現代では猛獣に出会うことはほとんどありませんが、脳にとっての「脅威」は、現代にも形を変えて存在しています。
たとえば――
● 人から攻撃的な言葉を投げかけられる
● 否定される、無視される
● 理不尽な扱いを受ける
こうした体験も、脳にとっては「命の危険」と同じレベルの脅威として感じられるのです。
なぜかというと、人間は「社会的つながり」の中で生きる生き物であるため、上記のような出来事は自分の立ち位置や居場所を脅かしかねない脅威だと神経が認識するからです。それで強く怒ることで自分を守ろうとするのです。
でも、現実的には怒ることで自分の身を守るというより、ますます自分の立場や関係性を悪くしたり、後で後悔して嫌な思いをすることもあります。
また、同じ出来事が起きても、すぐに怒り出す6秒ルールが効かない人と、6秒ルールでうまく怒りをコントロールできる人がいます。
これらの疑問は、わたしたちの自律神経(ポリヴェーガル理論)を知ると「なるほど!」スッキリわかっていただけるのですが、その詳しい説明は別の記事で書きたいと思いますから、ここでは、エッセンスをかいつまんでお話していきます。
怒りやすい・怒りがコントロールしにくい人とは?
怒りのコントロールが難しい人には、神経の働きにいくつかの特徴があります。
代表的なものを説明します。
① 過覚醒(かかくせい)タイプ
心身が常に強い不安や緊張の状態にあり、些細な刺激にも敏感に反応してしまう場合です。
ストレスやプレッシャー、睡眠不足が続くと、自律神経が乱れて、リラックスしたり休んだりすることができなくなってしまいます。
すると、イライラして、些細なことにも脅威を感じやすくなり、怒ってばかりになるのです。
「いつも気が張っている」「何かに追われている感じがする」という人は、このタイプかもしれません。
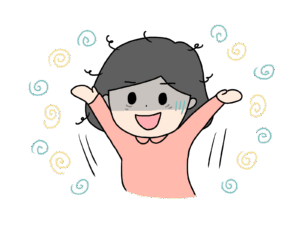
② 「耐性の窓」が狭いタイプ
私たちの自律神経には、「落ち着いて対応できる範囲(=耐性の窓)」があります。
自律神経が整っていると、人は、自然と緊張・興奮の後に力を抜いてリラックスしたり、おしゃべりやスポーツ、好きなことをして気分転換をしたりすることができます。このように、自然と自律神経のメンテナンスができている人は、不意の脅威に遭っても、すぐに怒り出すのではなく、6秒の間に冷静に考えて判断するゆとりを持つことができます。
耐性の窓は、心身のコンディションが整っていることに加えて、心理的な安全性が確保されていることや、基本的な対人信頼感があること、脅威に対処するためには怒るより相手と冷静に話し合える方が良い結果を生むことを体験から知っていることなどによって確保されます。
逆に、慢性的な疲労やストレス、慢性的なトラウマ体験(親子関係、いじめやハラスメント)は、耐性の窓を狭める要因です。

③ 腹側迷走神経がうまく働いていないタイプ
腹側迷走神経(ふくそくめいそうしんけい)というのは、副交感神経(リラックス)の1つです。
哺乳類(親が子どもを育てる種)が誕生したときに生まれた新しい副交感神経で、人間が生まれた時には未発達な状態ですが、親に温かくお世話をしてもらうことや友だちと楽しく遊ぶ体験などを通じて育まれます。
腹側迷走神経、というのは、安心して人とつながることを求める、そうできると落ち着ける、という安心とつながりの自律神経です。
この腹側迷走神経が育っていない、または働きにくい状態だと、危険ではない場面でも「脅かされている」と感じやすくなります。
結果として、相手の表情や言葉に過敏に反応し、強い怒りが出やすくなります。

怒りをコントロールするために大切なこと
怒りが脳と自律神経の反応であり、疲れやストレス、生育歴やトラウマ体験の影響を受けやすいことや、脅威に対処する防衛反応であることがお分かりいただけたでしょうか。
怒りを悪いものだと考えて押さえ込もうとしても、うまくいきません(なにせ0.5秒で発動するのですから!)
そうではなくて、怒りをコントロールするためには、自律神経を整えることが何より大切なのです。
まずは、しっかり寝て、3度の食事をしっかり摂ること、身体を動かすこと。休息の時間を設けること。
それから、腹側迷走神経を整えて、心と身体が「安全だ」と感じてリラックスできるようになることが大切です。
腹側迷走神経がちゃんと働いていると、脅威がきても瞬間湯沸かし器にならないで、ひと呼吸おくことができたり、無用に相手を傷つけたり(後で後悔しますよね)、不要に人を攻撃したり(敵を増やして生きづらくなります)するのを回避できるようになるのです。
腹側迷走神経を育てる・働かせるにはどうすればいいのか、というのは、ポリヴェーガル理論を理解していただくのがよいですが、ここでは、説明は抜きに、効果のあること、ぜひやってみてほしいことを10個ご紹介します。
① 10秒呼吸法
まず、身体の中にある息を「ふーっ」と吐きだします。
次に、1・2・3とカウントしつつ、鼻からゆっくり息を吸います。
カウント4で少し息を止めます。
そして5・6・7・8・9・10のカウントで、ゆっくりと息を吐きます。
コツは「吸うよりも、吐くことを意識する」こと。シャボン玉をそっとふくらませるように、ゆっくり・長く・やさしく息を吐きます。
吸うときは、おなかがふくらむように息を入れると、より深い呼吸になり、リラックスしやすくなります。
浅い呼吸の習慣がついていると最初はうまく深呼吸ができません。まずは、下腹を膨らませて吸う練習で腹横筋を作るところから始めていきましょう。

② バタフライハグ
バタフライハグは、両手を胸の前で交差させ、左右交互にトントンと肩のあたりをたたくことで、心と身体を落ち着かせるセルフケアです。
トントンたたく動きが、蝶が羽ばたくような姿に似ていることからこの名前がつきました。
まず、背筋を伸ばします。そして両腕を胸の前で交差して、左右の手を反対側の上腕や肩、または胸に添えます。
左右交互にトントンと、心地よい強さでたたき、呼吸を整えながら2分ほど行います。

③ くるまる・抱きしめる
肌触りの良いタオルケットや毛布にくるまります。

④ グラウンディング
グラウンディングとは、「地に足をつける」という意味で、不安やストレスを感じたときに心を落ち着かせるリセット法です。
■顔を上げて空を眺めてみましょう。晴れた日には空の青さを、曇りや雨の日には雲の動きを、ただそのまま感じてみてください。悩みや不安とは関係なく流れていく雲の様子が緊張を解き、こころに落ち着きを取り戻させてくれます。
■遠くの音に耳を澄ませましょう。鳥の鳴き声、子どもたちの笑い声、風の音や雨音などを探します。自然で安心感のある音は安全と結びついており、脳が「危険はない」と感じることで交感神経の緊張がゆるみ、腹側迷走神経が優位になります。
■鼻からゆっくり息を吸って、匂いを感じます。日なたや雨上がりの匂い、季節の花の香り。自然と呼吸が深まり、肩の力が抜けて、自律神経が整います

⑤ 目のエクササイズ
【1つ目】
3秒ほどぎゅっと目をつぶってから、ゆっくり力を緩めて目を開けます。
これを2〜3回繰り返しましょう。
目を閉じると、外部からの光や刺激が遮断されて脳の興奮が静まります。
【2つ目】
顔を動かさずに視線だけを左右や上下にゆっくりと動かし、部屋の中のものを順番に見渡してみましょう。
人は不安や緊張を感じると視野が狭くなり、目を一点に固定してしまいます。
キョロキョロエクササイズは「外の世界は安全だよ」と自律神経に伝えられます。
温かい飲み物をフーフーしながら飲む
熱い飲み物を「フーフー」すると、自然と吐く息が長くなります。
すると、心拍がゆっくりになって、副交感神経が穏やかに働きます。
熱い飲み物を少し冷ましてから飲もうと待つこと自体が、過覚醒で緊張した神経にブレーキをかけてくれます。

ハミング
口を閉じて鼻から息を出しながら「ふん〜」と声を響かせると、喉や胸、顔の奥にやさしい振動が広がります。この振動が、声帯や喉、胸のあたりを走る腹側迷走神経を穏やかに刺激して、心拍や呼吸を落ち着けます。
人は声や穏やかな音を「安全」と感じるため、自分の身体の中から響くやわらかい音でリラックスできます
ハミングでは息をゆっくり長く吐くので、自然と呼吸のリズムが整い、腹側迷走神経がよく働きます。
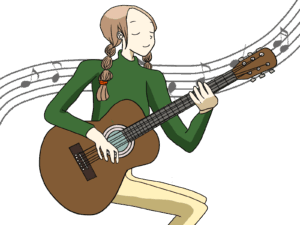
自然に触れる
空や木々、風や水の音などの“自然のゆらぎ”は、私たちの神経を穏やかに整えてくれます。
朝や昼休みに少し外を歩いたり、ベランダから空を見上げたりするだけでも効果があります。
というのも、自然のリズムは私たちの体内リズムと共鳴して、呼吸や心拍を落ち着け、腹側迷走神経を優位にしてくれるからです。

動物に触れる
動物は人を脅かしたり評価したりしない「安全な存在」です。
対人関係に疲れた自律神経を穏やかに緩めてくれます。
また、動物の動きや声のリズムに人の神経が同調して呼吸や心拍が整います。
ただ一緒にいるだけで腹側迷走神経が優位になって安心を感じられます。
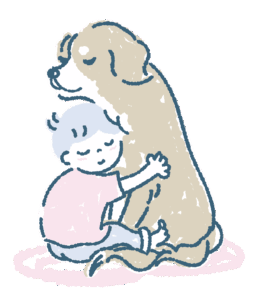
信頼できる人とおしゃべりする
人と安心して話すとき、私たちの身体では腹側迷走神経が働いています。
穏やかな声で話したり、相手の優しい声を聞いたりすると、脳が「安全だ」と判断して交感神経の緊張がゆるみ、心拍や呼吸が整います。
ぜひ、信頼できる人とのたわいのないおしゃべりを楽しんでください。

6秒ルールで怒りをコントロールする方法・まとめ
怒りは「悪い感情」ではなく、私たちの神経が危険から身を守ろうとする自然な反応です。
けれど、疲れやストレスで自律神経のバランスが崩れていると、ほんの小さな刺激にも過剰に反応してしまいます。
怒りを抑え込むよりも、自律神経を整えて「安心できる身体」に戻すことが大切です。
ご紹介したセルフケアは、誰でも今日からできるとても効果的な方法です。
まずはできるところから、あなたのペースで試してみてくださいね。
ただ、
✔️一時的には落ち着くけれどすぐに元に戻ってしまう
✔️感情の波が強すぎてセルフケアに取りかかれない
✔️怒りやすさの背景に、これまでの経験や人間関係のつらさが関係している気がする
そんな場合は、ひとりで抱え込まないでください。
あなたの怒りや生きづらさには、必ず「理由」があります。
カウンセリングでは、その理由を一緒に紐解きながら、自律神経を整え、安心して過ごせる時間と人間関係を作るお手伝いをしていきます。
怒りのコントロールは、意志の力ではなく、自律神経を整えながら、安心感・信頼感を再獲得するプロセスなので、信頼できるサポートを得ることが結果を出しやすくします。
はこにわサロンでも、あなたのお話をていねいに伺いながら、怒り、ストレス、人間関係、トラウマケアなど、状況に合わせてサポートをしています。
「どうしたらいいのかわからない」
「ひとりで頑張るのに限界を感じている」
そんなときは、どうぞ気軽にご相談くださいね。
▶︎ はこにわサロンについて
▶︎ ご予約はこちら
あなたが「ご自分らしさ」を失わずに、怒りと上手につきあっていかれますよう並走します。
どうぞ、お気軽にご相談ください。