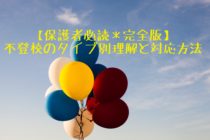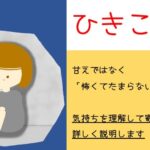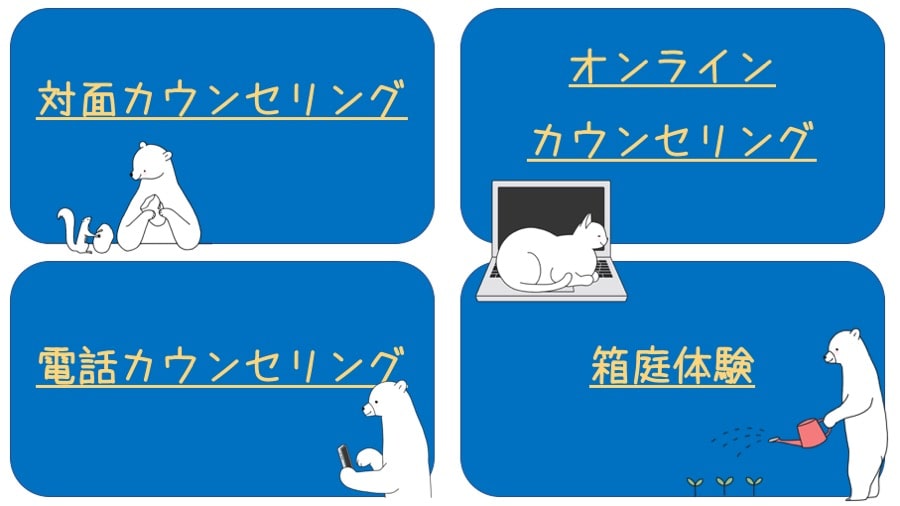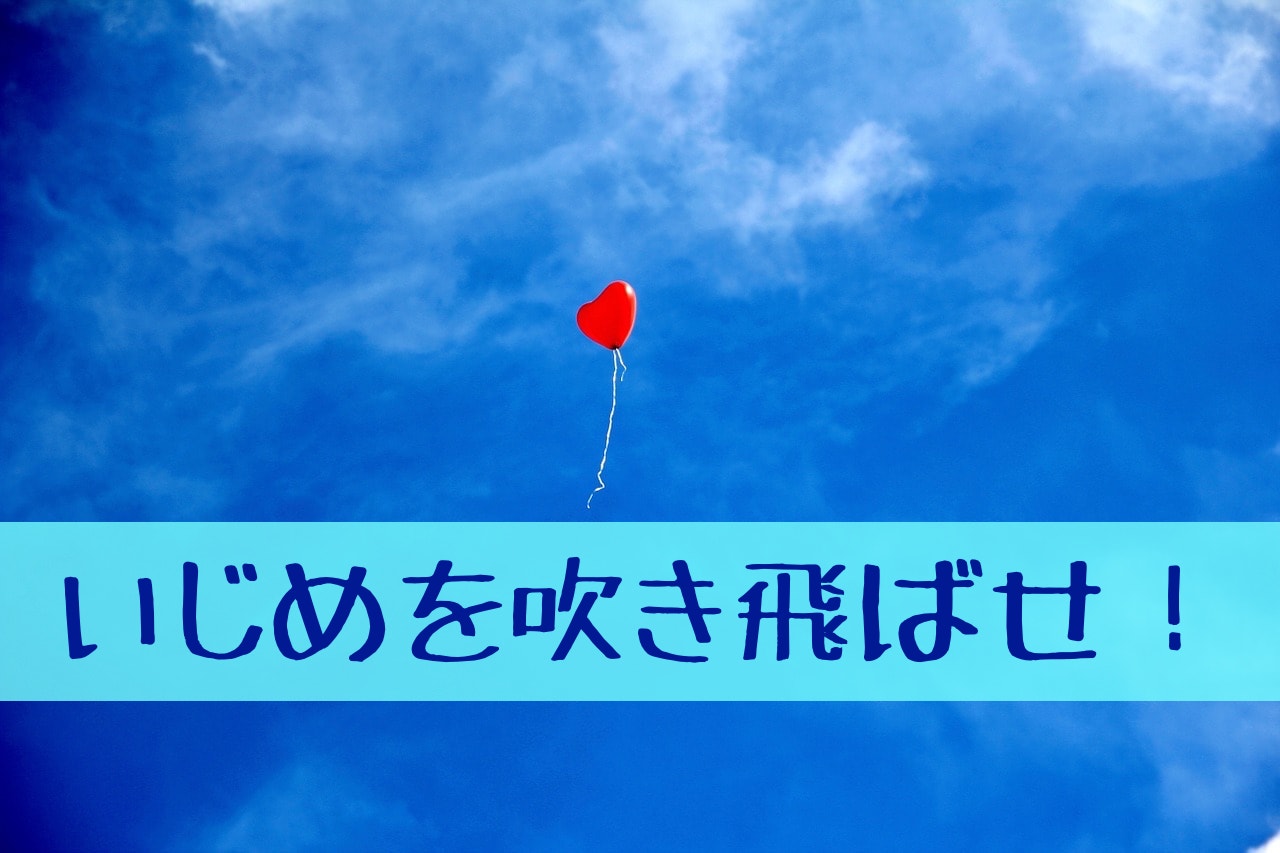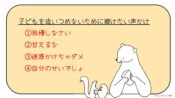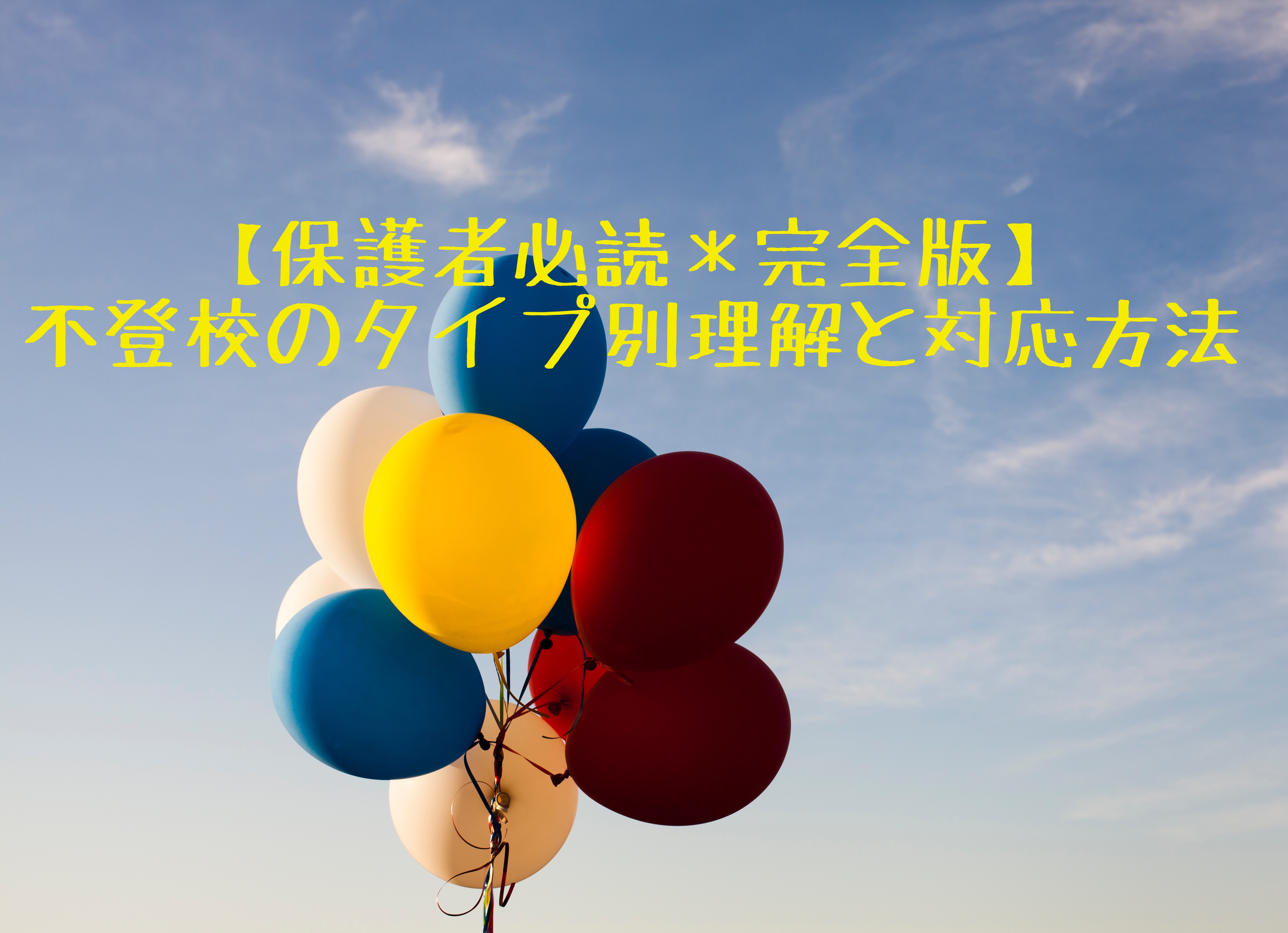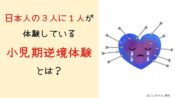不登校の子どもの気持ちを知りたいと思ったときに読んでみて欲しい本

子どもと親の不登校カウンセリングを行っています(東京・青山一丁目)
 臨床心理士としてスクールカウンセラーをしている吉田です。
臨床心理士としてスクールカウンセラーをしている吉田です。
「不登校になった子どもが、インターネットで”不登校”を検索しています」
こうお話ししてくださったお母さんがいらっしゃいました。不登校になる子どもの多くは、自分でもなぜ学校を休んでしまうのかよくわからないことが多いと感じます。
インターネットで検索したり、同じ不登校の子どもと会っても、なかなか自分と全く同じ理由や気持ちの子と出会うのは難しいのではないかと思います。
でも、なんとか答えを見つけたいと願って探したり、少しちがう・少しだけ同じ体験を見つけて、自分と照らし合わせ、対話することは大切なのではないかと思います。
インターネットの記事も悪くはないのですが、不登校を題材にした本の中にも、共通体験のできる作品があります。今日は、そんな何冊かの本をご紹介します。
● 自分のことを理解したいと思っている不登校の子ども
● 不登校の子どもの気持ちを理解したいと思う大人
本屋大賞受賞の『かがみの孤城』は本に夢中になる楽しさを思い出させてくれる
冒頭のお母さんにわたしがご紹介したのがこの本です。今年の本屋大賞を受賞した話題性もあって、手に取りやすいし、何より夢中になって読めるストーリー展開で、読書の面白さを味わってもらえるからです。
現実の世界で居場所のない子どもたちが、不信を乗り越えて協力しあい、それぞれに自分の世界に復帰して行くのですが、そこにはあっと驚くねじれがあるのです。
不登校のきっかけ: いじめ
復帰のきっかけ: 「たかが学校」と思えるようになったこと
『西の魔女が死んだ』に描かれる魔女修行
ストーリーテリングの面白さで言ったら、この本も負けてはいません。映画で観た方も多いかもしれません。
学校に行けなくなったまいが、おばあちゃんの家で魔女修行をするというお話です。まいの不登校の理由はあまり語られません。でも、自分の世界を持つ大人っぽさと、幼い頑固さが共存するしんどさは、不登校の子どもたちにもよく見られるような気がします。
また、日常生活を建て直すことや、揺るがない自分を獲得しようとする”魔女修行”は、不登校からの(あるいは揺らぎの多い思春期を超えていくための)方法であるように思います。
不登校のきっかけ: 仲間はずれ
復帰のきっかけ: お父さんの赴任先に家族が転居しての転校
母親の葛藤をていねいに描いている『黄色い髪』
この本は、だいぶ昔の本です。わたしが持っている文庫本の初版は1989年(平成元年)です。けれど、中学生の悩みはいまも昔も変わらないと改めて感じました。そして、学校の持つ性質も、あまり変わっていないなとも感じました。
自分が当たり前と思ってやっていることが、周囲の子どもたちには「いい子」「優等生」に見える。先生からも「異分子」と指導される。そんな残念な出来事が続き、主人公の夏実は学校に行くことを止めるのです。

この本の特徴は、主人公の夏美と並列して、母親の葛藤をていねいに描いていることだと思います。母親が心配して夏美と向き合いたいと思っても、夏美は応じることができません。自分でもどうすればよいか全くわからなくて混乱しているけど、誰にも助けてもらえない(自分で悩み抜くしかない)のです。
夏美から避けられてしまった母親は、夏美を理解しようとして、夏美の周りの人たち(先生や友だち、その親)に話を聞いたり、街中を徘徊する子どもたちに寄り添ったりします。そうして、悪者がいるのではないことや、もがき苦しんでいる夏美を助けたくても助けられないことに気づいていきます。
久しぶりに親子で話をすることができた時、夏美は「母親を階段から突き落とす夢を見た」と話します。「親離れ」は、心理的には「親殺し」として体験されることも少なくありません。それくらい壮絶で、両者にとって血みどろの取っ組み合いになることもあるのだと思います。
最後に・・・夏美のお父さんは、夏美が小さい頃に病気で亡くなっているのですが、この辛い時期をお父さんがこっそりと支えてくれているのです。どんな風にか?は読んでのお楽しみです。
不登校のきっかけ: 陰湿ないたずら
復帰のきっかけ: 自分を信じて生きられるようになったから
壮絶な戦い〜『14歳』
不登校未満の子どもの成長を描いた『うさぎとトランペット』
この本の主人公、宇佐子(小学校5年生)は新学期そうそう、原因のはっきりしない発熱で学校を休みます。それは「子どもから大人へ変わるよ」という身体からのメッセージのようです。
セラピストも繰り返し読んでいる『はてしない物語』
以前こちらでも取り上げたことがありますが、このエンデの物語は、自分のことが好きになれない、居場所のない子ども(と大人)のための、成長の手ほどき書ではないかと思います。
主人公のバスチアンは、自分の人生から逃げ出すのですが、その時に訪れた「ファンタジーエン」で、「英雄になること」と「親友を得ること」、「失敗をくりかえすこと」、「無条件の愛情を得ること」、「自分の弱さに立ち向かうこと」を経験して、戻ってきます。そして、自分を心配してくれたお父さんと再会することができます。
もちろんこの物語はファンタジーなのですが、不登校の子どもたちの心の中では、言語化されなくても似た体験がされていることも少なくありません。