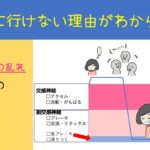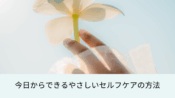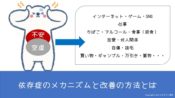起立性調節障害とは?―朝起きられない子どもたちのサポート方法

東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。
「朝起きられない」「学校に行こうとすると具合が悪くなる」「午前中はぼーっとして何もできない」子どもがそんな訴えを繰り返すと、「サボっている」「甘え」ではないかと考えてしまうかもしれません。でも、それは、起立性調節障害かもしれません。
起立性調節障害は、思春期に多くみられる自律神経の不調で、生活や学業に大きな影響を与えることもあります。
この記事では、起立性調節障害の基本的な知識と、子どもを支えるために大切なことをまとめます。
起立性調節障害とは
起立性調節障害とは、立ち上がった時に血圧や脈拍がうまく調整されず、めまいや倦怠感などの症状が現れる自律神経の機能障害です。
特に朝の時間帯に強く症状が出やすく、「登校できない」「午前中は何もできないけれど、午後からは元気」という特徴があり、本人も周囲も混乱することがあります。

起立性調節障害の原因
原因は一つではなく、以下のような要因が複雑に関係しています。
成長期における自律神経のアンバランス
思春期は、身長が急に伸びたり、ホルモンバランスが大きく変化したりと、身体の内外で変化が著しい時期です。
この変化に自律神経(交感神経と副交感神経のバランスをとる働き)が追いつかず、血圧や心拍、体温、睡眠の調整がうまくいかなくなることがあります。
特に、背が急に伸びる時期は、重力の影響で脳に血液が届きにくくなるため、立ちくらみやふらつきなどが起こりやすいとされています。つまり、「体が成長している途中で、自律神経がうまく調整できない」こと自体が、症状の大きな背景になっているのです。
ストレスや環境の変化
自律神経は、こころの状態とも密接に関わるため、心理的なストレスがかかるとすぐに影響を受けます。
たとえば:
■学校の勉強や人間関係のプレッシャー
■部活動や塾などでの過密スケジュール
■家庭内の不和や過干渉・過保護
■親からの「ちゃんとしなさい」「なまけてるんじゃないの?」という言葉
こうしたストレスが積み重なると、副交感神経の働きが弱まり、交感神経が過剰に働き続ける状態=常に“緊張モード”になってしまうのです。
結果として、朝起きづらい・疲れやすい・頭痛がするなどの身体症状が現れやすくなります。
体質的な要因(もともとの身体の特徴)
起立性調節障害は、体質や個人差の影響も大きい病気です。
たとえば:
■もともと低血圧傾向で、立ち上がるとふらつきやすい
■筋力や持久力が弱く、体が疲れやすい
■胃腸が弱いなどの傾向がある
こうした体質のある子は、自律神経の調整もうまく働きにくいため、起立時の循環調節に時間がかかり、血圧が下がったままになってしまうことがあります。
このように、起立性調節障害の背景には、成長期特有の生理的変化+心理的ストレス+体質が重なり合っています。
「気持ちの問題」や「根性の問題」として叱ってしまうのではなく、身体と心の両面からサポートすることが大切です。

起立性調節障害の症状
起立性調節障害の主な症状には、次のようなものがあります。
■朝なかなか起きられない(午前中の強い眠気・だるさ)
■立ちくらみ・めまい・ふらつき
■動悸・息切れ
■頭痛・吐き気・腹痛
■食欲不振
■午後になると元気になる(午後型の活動パターン)
■入浴や運動後にぐったりする
■寝つきは悪くないが、起床が困難
■集中力・学力の低下、登校困難・不登校
これらは「気のせい」「怠け」と誤解されやすいですが、実は身体的な問題です。
起立性調節障害の診断
診断には、小児科や心療内科・内科での診察が必要です。以下のような検査や問診を通して判断されます。
■問診・生活状況の聴き取り
朝の様子や日中の過ごし方、ストレス要因などを確認します。
■新起立試験(10分間の起立負荷テスト)
血圧や心拍の変化を測定し、立位での循環調整の異常をチェックします。
起立性調節障害のチェックリスト(簡易版)
以下に当てはまる項目が多い場合、起立性調節障害の可能性があります(目安としてご利用ください)。
□ 朝、なかなか起きられない/起こしても反応がない
□ 午前中はぼーっとして元気がないが、午後から元気になる
□ 立ちくらみやめまいがよくある
□ 頭痛や腹痛をよく訴えるが、検査で異常はない
□ 通学や授業への集中が難しい
□ 入浴後に気分が悪くなる
□ 食欲がない/低血圧気味
□ 不安が強く、学校のことを考えると体調が悪くなる
※3〜4項目以上あてはまる場合は、専門機関への相談をおすすめします。

起立性調節障害の治療
起立性調節障害の治療は、本人の体調や生活リズムに合わせて、無理のないかたちで整えていくことが大切です。
そのため、治療は薬だけに頼るのではなく、生活・環境・心理的な支援も含めた“総合的な対応”がとても重要になります。
生活を整えること
早寝・早起きの習慣をつける ―「起きやすくなる環境づくり」から
■夜はスマホやゲームは1時間前までにオフ。画面の光が睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を妨げます。
■寝る30分前から照明を少し暗くする、アロマや落ち着いた音楽を使って「おやすみ儀式」をつくる。
■朝は強い光を浴びることで体内時計がリセットされるので、カーテンを開ける・ライトを使って部屋を明るくするのもよい。
朝食を摂る ― 塩分と水分を意識して
■朝一番にコップ1杯の常温の水や経口補水液(OS-1など)を飲む。
■食べやすいもの、食べたいものを準備する。
■食欲がない場合は、ジュースやスープ、お味噌汁も◎
無理のない運動習慣
■朝や夕方に、5分のストレッチタイム。親子で一緒にやると続きやすい。
■好きな音楽に合わせるとやる気が出ます。
■ベランダに出て深呼吸・光を浴びるのもよいです。
■体調がいい日は、「歩いて5分のコンビニでおやつを買う」など、楽しめる外出をする。
どれも「できる日もあれば、できない日もある」ことを前提にし、「できたらOK」「できなくても責めない」が何より大切です。

薬物療法
医師の判断で、症状が強い場合にはお薬が処方されることもあります。
■昇圧薬(血圧を上げる薬)
■自律神経調整薬
これらは、一時的に体調を安定させる手助けになります。薬の使用は、生活の改善や心のケアとあわせて行うとよいでしょう。
環境調整
学校や家庭の環境を柔軟に調整することも、子どもが無理なく生活を送るために不可欠です。
学校との連携
■登校時間を遅らせる、登校頻度を減らすなど、学校と相談して無理のない登校の方法を検討してください。
■相談は、担任の先生や養護教諭の他、スクールカウンセラーに相談することができます。
■学校によっては、別室に登校することができたり、地域の適応指導教室に登校することが可能です。相談してみてください。
■フリースクールを探してみるという方法もあります。フリースクールの登校を学校の登校として認めてもらえる場合がありますから、学校に相談してみるとよいでしょう。

起立性調節障害の回復のためにカウンセリングにできること
起立性調節障害は身体の病気ですが、症状の長期化や不登校がこころの負担になることも多く、心理的支援がとても重要です。
カウンセリングでは、
■「自分はダメだ」と思わないようにサポートする
■自己肯定感を育てる
■不安や罪悪感を整理し、自分のペースで回復する力を取り戻す
■家族との関係を調整し、安心できる居場所を整える
といった支援を行います。
特に、自分を責めやすい子や「友達と差がつく」「迷惑をかけている」と感じやすい子ほど、共感と肯定をベースにした関わりが必要です。
子ども本人にはカウンセリングを実施できないことも多いです。その場合、ご家族がカウンセリングで、子どもの様子についてや、家庭でできることなどについて相談することも大切です。保護者のサポート疲れや孤独感が生じやすいこともありますから、おひとりで抱えてしまわずにご相談ください。

起立性調節障害の回復のために自分でできること
少しずつ体調を整えるために、以下のようなセルフケアも役立ちます。
■起きる前に布団の中でストレッチや手足を動かしてみる
■朝、コップ1杯の水を飲む
■寝る前のスマホ・ゲームを控える
■自分に優しくする言葉を持つ(例:「今日はここまでできたね」)
■好きなことに取り組む時間を持つ
■自分の気持ちを書いてみる
最初から全部をやろうとせず、「今日は1つやってみよう」くらいの気持ちが大切です。

起立性調節障害の回復のために家族にできること
起立性調節障害の子どもにとって、何より大きな支えになるのが家族の理解とサポートです。
■「怠けている」「学校に行けないと困るよ」など、子どもを否定する言葉をかけるのはやめましょう
■朝、無理に叱って起こさない(症状を悪化させる場合も)
■「今日はどう過ごそうか」と寄り添いながら予定を立てる
■子どもの声をよく聴き、安心できる雰囲気をつくる
■学校や医療との連携して対応方法を検討する
「なまけているのではなく、がんばりたくてもこころも身体もがついてこないつらい状態なんだ」と理解すること、「時間はかかるが、必ず健康を取り戻すことができる」と明るい見通しを持つことが大切です。
でも、そう考えることが難しい時もあると思います。その場合は、どうぞ、信頼できる相談者につながってください。親が追い詰められて孤独になると、子どもにぶつけてしまいやすくなり、悪循環になってしまうので、ご注意ください。
起立性調節障害・おわりに
起立性調節障害は、見た目ではわかりにくいために誤解されやすい病気です。でも、それは「意志の弱さ」ではなく、成長期に誰にでも起こり得る身体の不調です。
正しい理解と支援があれば、必ず回復していきます。子どもたちが「わたしのことをわかってくれる大人がいる」と思えることが、回復の土台になります。焦らず、少しずつ、一緒に歩んでいきましょう。
はこにわサロンでは起立性調節障害についてのご相談を受け付けています。
ご予約はこちらから。